サイトのリニューアルや修正、ワクワクしますよね。でも、ちょっと待ってください!そのままメンテナンス画面を出すだけだと、せっかく積み上げた検索順位が下がってしまうかもしれません。「503 メンテナンス」というステータスコードを正しく設定することが、SEOを守る鍵なんです。
「サイトを一時停止したいけれど、SEOへの悪影響が心配」「正しい設定方法がわからない」と悩んでいませんか?
この記事では、初心者の方でも安心して設定できるよう、503の意味から具体的な設定手順まで、優しく解説します。正しい手順を踏めば、検索エンジンからの評価を維持したまま、安全にメンテナンスを行えます。さあ、一緒にサイトを守る準備を始めましょう。
このページに書いてあること
メンテナンス時に重要なステータスコード503とは
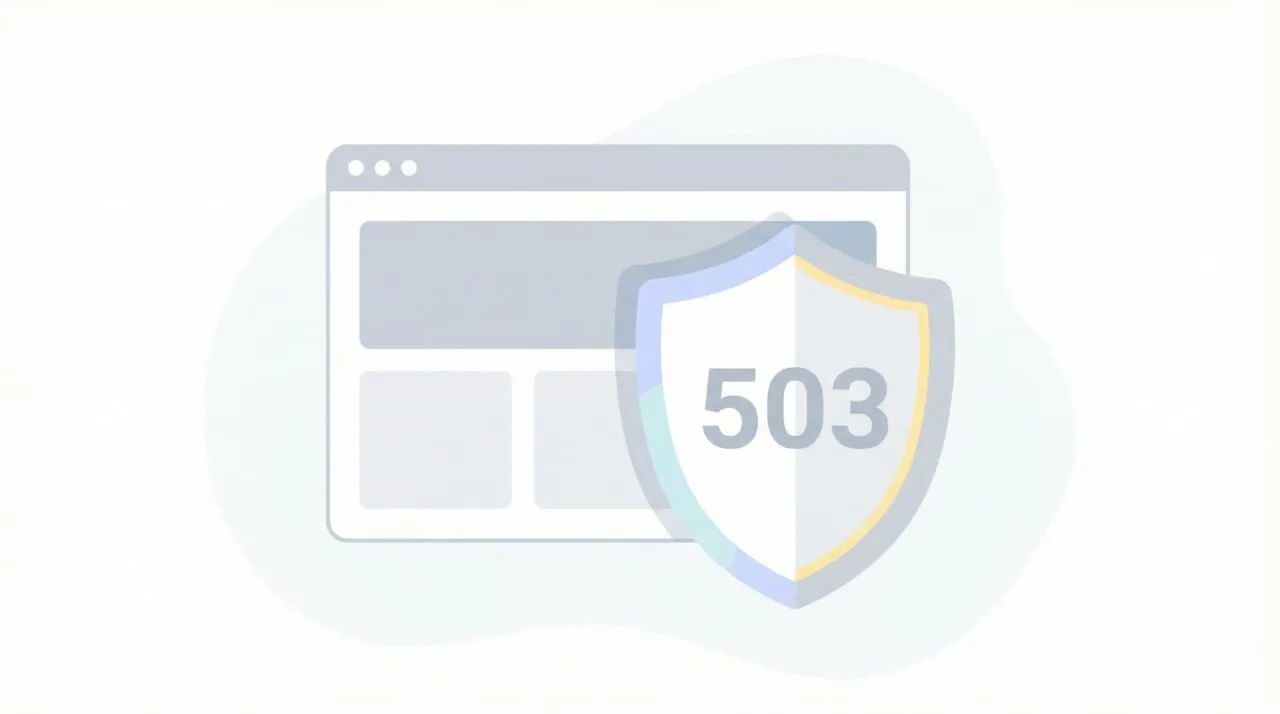
Webサイトの運営において、「503」という数字はとても大きな意味を持っています。普段はあまり目にしないかもしれませんが、メンテナンス時にはこのコードがサイトの命運を握ると言っても過言ではありません。まずは、このステータスコードが持つ本来の意味と、なぜメンテナンス時に必要なのかを理解しましょう。
ステータスコード503(Service Unavailable)の意味
ステータスコード503は、正式には「Service Unavailable(サービス利用不可)」と呼ばれます。これは、サーバーへのアクセスが集中しすぎて処理しきれない場合や、メンテナンス中で一時的にサービスを提供できない状態であることを示すものです。
簡単に言えば、Webサーバーが「今はちょっと忙しい(または準備中)だから、あとでまた来てね」と訪問者に伝えている状態ですね。エラーの一種ではありますが、サイトが壊れているわけではなく、あくまで「一時的な停止」であることを意味しています。
なぜメンテナンス画面で503を返す必要があるのか
メンテナンス画面を表示する際、ただ「工事中」という画像やテキストを見せるだけでは不十分です。裏側で動いているシステム(サーバー)が、正しい信号を発信しているかが重要になります。
もし503を返さずに画面だけ切り替えてしまうと、検索エンジンやブラウザは「これがこのサイトの正常な状態なんだ」と誤解してしまうかもしれません。ユーザーには「メンテナンス中」と表示しつつ、システム的には「503(一時停止中)」という正しいステータスコードを返すことが、Web運営の正しいマナーと言えるでしょう。
検索エンジンに「一時的な停止」と伝える重要性
Googleなどの検索エンジンロボット(クローラー)は、定期的にあなたのサイトを巡回しています。このとき、メンテナンス中のサイトから503が返ってくると、クローラーは「なるほど、今は工事中なんだな。また後で確認しに来よう」と判断してくれます。
これにより、一時的にサイトが見られない状態であっても、検索結果の順位や評価を落とさずに済むのです。逆にこの信号がないと、「サイトの内容がなくなった」あるいは「質が低下した」と判断されかねません。検索エンジンと正しく対話するために、503は欠かせない言葉なのです。
503とSEOの関係性と検索順位への影響

SEO(検索エンジン最適化)に取り組んでいる方にとって、メンテナンス期間は緊張するタイミングですよね。適切な処置をしないと、これまで積み上げてきた評価が一瞬で崩れてしまうリスクがあります。ここでは、503ステータスコードとSEOの密接な関係について、もう少し掘り下げて見ていきましょう。
正しいステータスコードを返さない場合のSEOリスク
正しいステータスコード(503)を返さずにメンテナンスを行うと、検索エンジンはサイトにアクセスできない、あるいはコンテンツが空っぽになったと判断します。
最悪の場合、検索インデックス(データベース)からページが削除されてしまったり、検索順位が大幅に下落したりする可能性があります。一度失った評価を取り戻すには、多くの時間と労力が必要です。このようなSEOリスクを避けるためにも、メンテナンス時のステータスコード管理は必須と言えるでしょう。
404と503の違いとGooglebotの挙動
よくある間違いとして、ページが見つからないことを示す「404 Not Found」との混同があります。
- 404 (Not Found): ページが削除された、または存在しない(恒久的な消失)。
- 503 (Service Unavailable): 一時的にアクセスできない(将来的に復旧する)。
Googlebotは404を受け取ると、そのページをインデックスから削除しようとします。一方、503であれば「一時的なもの」としてインデックスを保持し、再訪問を試みてくれます。この違いはSEOにおいて決定的ですので、決して間違えないようにしましょう。
200 OKでメンテナンス中画面を出すことの問題点
また、ステータスコード「200 OK(正常)」のまま、「ただいまメンテナンス中です」という画面を表示するのも問題です。
これは「ソフト404」と呼ばれる状態になりやすく、検索エンジンは「メンテナンスのお知らせ」という内容自体を、そのページの正規のコンテンツとして評価してしまいます。つまり、「高品質な記事」が「メンテナンスのお知らせという薄いコンテンツ」に書き換わったと誤認されるのです。これではサイトの評価がガクンと下がってしまいますよね。
Webサイトでメンテナンス画面を表示する主な方法

では、実際にWebサイトでメンテナンス画面を表示し、かつ正しく503ステータスコードを返すにはどうすればよいのでしょうか。サイトの構築環境やあなたの技術レベルに合わせて、いくつかの方法があります。代表的な3つのアプローチをご紹介します。
WordPressのプラグインを利用して表示する
WordPressでサイトを運営している場合、プラグインを使うのが最も簡単で安全な方法です。「WP Maintenance Mode」や「Maintenance」などのプラグインを導入すれば、専門的なコードを書くことなく、数クリックでメンテナンスモードへの切り替えが可能です。
メリット:
- 設定が簡単で初心者向き。
- デザインのカスタマイズも容易。
- 503ステータスコードも自動で送出してくれるものが多い。
まずはこの方法を検討してみるのがおすすめですよ。
サーバーの設定ファイル(.htaccess)を編集する
ApacheなどのWebサーバーを使用している場合、「.htaccess(ドットエイチアクセス)」という設定ファイルを編集する方法が一般的です。これはサーバーの挙動を直接制御する方法で、WordPress以外の静的サイトなどでも利用できます。
特定のIPアドレス(管理者であるあなた)だけは通常通りサイトが見られるようにし、それ以外のユーザーにはメンテナンス画面を見せる、といった柔軟な設定が可能です。少し専門知識が必要ですが、非常に強力な方法です。
PHPなどのプログラムコードで制御する
PHPなどのプログラミング言語を使って、動的にステータスコードを出力する方法もあります。サイトのヘッダー部分にコードを記述し、条件に応じて503を返します。
例えば、特定の期間だけ自動で切り替えたり、データベースの接続状況に応じて表示を変えたりといった高度な制御が可能です。開発者がいる場合や、システム自体にメンテナンス機能を組み込みたい場合に適しています。
Apacheで503を設定する具体的な手順と記述方法
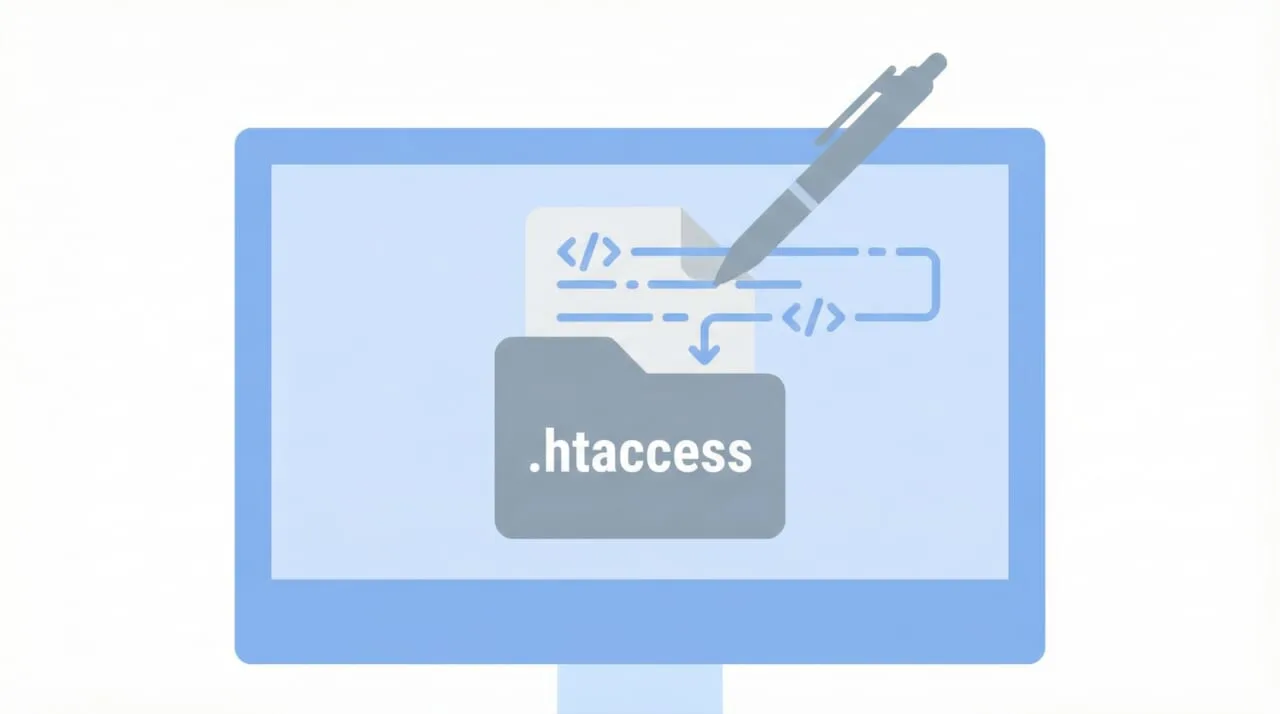
ここでは、多くのレンタルサーバーで利用可能な「.htaccess」を使って、手動で503を設定する具体的な手順を解説します。少しコードを触ることになりますが、コピペで使える例も紹介しますので、落ち着いて取り組んでみてくださいね。バックアップを取ってから作業することをお忘れなく。
ユーザーに表示するメンテナンスページ(HTML)の作成
まずは、ユーザーに表示するためのメンテナンス画面(HTMLファイル)を作成しましょう。ファイル名は maintenance.html など、分かりやすい名前にします。
内容はシンプルで構いません。「只今メンテナンス中です」というメッセージと、いつ頃終わるかの目安、お詫びの言葉などを記載します。デザインにこだわりたい場合は、CSSを使って整えても良いでしょう。このファイルをサーバーのルートディレクトリ(一番上の階層)にアップロードしておきます。
.htaccessにErrorDocument 503を記述する
次に、サーバーの設定ファイルである .htaccess を編集しましょう。このファイルに「アクセスしてきた人には503エラー(メンテナンス中)を伝えて、さっき作った maintenance.html を表示してね」という指示を書き込みます。
ただし、表示するページを指定するだけではメンテナンスモードとして機能しません。すべてのアクセスに対して強制的に503エラーを返す設定も一緒に書くことが大切です。
具体的には、以下のようなコードを記述してみてください。
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# メンテナンス画面自体は除外しないとエラーがループしてしまいます
RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/maintenance.html
# 画像やCSS、JavaScriptは表示できるように除外します
RewriteCond %{REQUEST_URI} !\.(css|js|jpg|jpeg|png|gif)$
# 自分のIPアドレス(管理者)は除外してサイトを確認できるようにする場合
# 以下の行の # を外して、自分のIPアドレスに書き換えてください
# RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !=123.456.78.90
# 上記以外のアクセスはすべて503エラーにします
RewriteRule ^.*$ - [R=503,L]
</IfModule>
# 503エラーの時に表示するファイルを指定
ErrorDocument 503 /maintenance.html
# 検索エンジンにメンテナンス終了予定を伝える(例:3600秒=1時間後)
<IfModule mod_headers.c>
Header set Retry-After "3600"
</IfModule>Code language: PHP (php)少し難しく見えるかもしれませんが、基本的にはこのまま使えば大丈夫でしょう。この設定を行えば、訪問者にはメンテナンス画面を表示しつつ、検索エンジンに対しても「一時的な 503 メンテナンス」であることを正しく伝えられます。管理者のIPアドレスを除外設定しておけば、裏側でサイトの動作確認もできるので安心ですね。
RewriteEngineを使ってメンテナンス画面へ転送する
続いて、すべてのアクセスに対してメンテナンス画面を表示しつつ、検索エンジンに「一時的な停止」を伝える設定を行いましょう。これには RewriteEngine(リライトエンジン)などの機能を使います。
以下の記述を .htaccess に追記してみてください。
ErrorDocument 503 /maintenance.html
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/maintenance.html
RewriteRule ^.*$ - [R=503,L]
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header set Retry-After "3600"
</IfModule>Code language: HTML, XML (xml)この設定により、maintenance.html 以外のページへのアクセスはすべて「503 メンテナンス」中として扱われ、用意したメッセージ画面が正しく表示されるようになります。SEOへの影響を抑えるための記述も含まれているので、安心して設定を進めてくださいね。
管理者のIPアドレスだけアクセス許可する設定
このままの設定だと、管理者であるあなた自身もサイトが見られなくなってしまい、メンテナンス作業が進められません。そこで、自分のIPアドレスからのアクセスだけは「503 メンテナンス」の対象外にして、通常通りサイトを表示させる設定を追加しましょう。
ErrorDocument 503 /maintenance.html
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
# メンテナンス画面自体は503の対象外にする
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/maintenance.html$
# 管理者のIPアドレス(例: 192.0.2.1)を除外する
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !=192.0.2.1
# 上記の条件に当てはまらないアクセスには503を返す
RewriteRule ^ - [R=503,L]
</IfModule>Code language: PHP (php)192.0.2.1 の部分は、あなたの現在のIPアドレスに書き換えてください。これで、あなた以外のアクセスには503エラーとともにメンテナンス画面が表示され、あなただけは通常通りサイトを閲覧や操作ができるでしょう。
なお、一般的なインターネット回線ではIPアドレスが定期的に変わることがあります。もし急にアクセスできなくなった場合は、IPアドレスが変わっていないか確認してみてくださいね。
SEO評価を守るための503設定のポイント
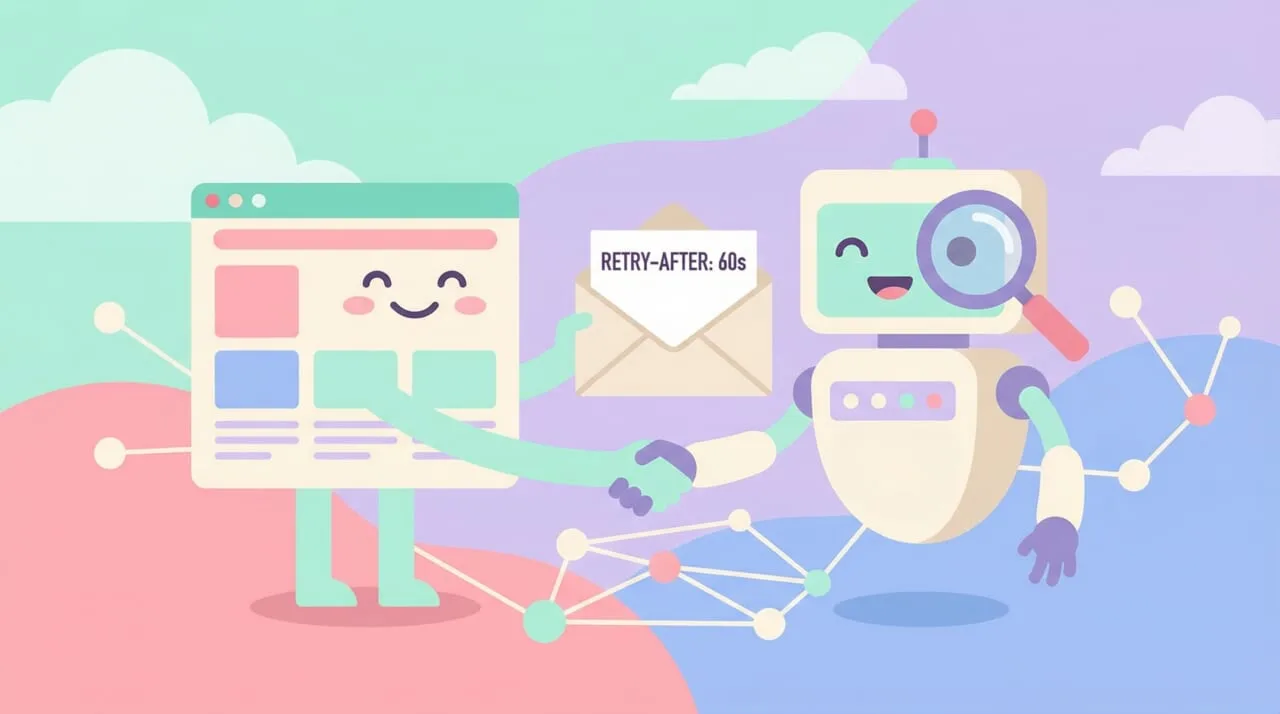
503の設定は「ただ返せばいい」というものではありません。検索エンジンに対して、より丁寧な情報を伝えることで、SEOの評価をさらに確実に守ることができます。ここでは、ワンランク上の設定ポイントをご紹介します。
Retry-Afterヘッダーで再クロールのタイミングを伝える
503を返す際、HTTPヘッダーに Retry-After という情報を付与することができます。これはクローラーに対して「〇〇時間後(または〇〇日)にまた見に来てね」と、再訪問のタイミングを指定するものです。
これを設定しておくと、Googlebotなどのクローラーが無駄なアクセスを繰り返すのを防ぎ、指定した時間に効率よく再クロールしてもらえる可能性が高まります。.htaccessの設定でヘッダーを追加記述することで実現できます。
サイト復旧後は速やかに503設定を解除する
メンテナンスが終わったら、すぐに503の設定を解除することを忘れないでください。作業が完了しているのに503を返し続けていると、ユーザーがアクセスできないだけでなく、検索エンジンも「まだサイトが復旧していない」と判断し、検索結果に表示されなくなってしまいます。
作業終了後は、.htaccessの記述を削除またはコメントアウトし、正常にサイトが表示されるか必ず確認しましょう。
メンテナンス期間が長期化する場合の注意点
503はあくまで「一時的な」停止を示すものです。もしメンテナンスが数週間や数ヶ月といった長期間に及ぶ場合、検索エンジンは「このサイトはもう復旧しないのではないか」と判断し、インデックスから削除してしまう可能性があります。
長期のメンテナンスが必要な場合は、サイトの一部だけを閉鎖して主要なコンテンツは残すなど、別の対策を検討する必要があるかもしれません。基本的には、503の状態は数日程度にとどめるのが理想的です。
正しく503が返されているか確認する方法

設定作業が終わったら、必ず動作確認を行いましょう。「画面が切り替わったからOK」と思い込むのは危険です。裏側で正しいステータスコードが返ってきているか、しっかりとチェックする方法をお伝えします。
Google Chromeのデベロッパーツールで確認する
Google Chromeなどのブラウザに搭載されている「デベロッパーツール」を使うと、実際の通信状況を確認できます。
- F12キーを押してデベロッパーツールを開く。
- 「Network」タブを選択する。
- ページを再読み込みする。
- 一番上のファイル名をクリックし、「Status」の項目を確認する。
ここに「503 Service Unavailable」と表示されていれば、設定は成功です!
オンラインのHTTPステータス確認ツールを使う
ブラウザの操作が難しく感じる場合は、無料で使えるオンラインの確認ツールを利用するのが便利です。「HTTPステータスコード チェッカー」などで検索すると、多くのツールが見つかります。
使い方は簡単で、自分のサイトのURLを入力してボタンを押すだけ。サーバーが返しているレスポンスコード(200や404、503など)を瞬時に表示してくれます。客観的に確認できるのでおすすめですよ。
Search ConsoleのURL検査ツールを活用する
Google Search Console(サーチコンソール)に登録している場合は、「URL検査ツール」を活用しましょう。
メンテナンス中のページのURLを入力して検査を実行すると、Googlebotがそのページにアクセスした際の結果が表示されます。「ページの取得」の項目でステータスがどうなっているかを確認できます。Googleの視点でチェックできるので、SEO的には最も確実な確認方法と言えます。
ユーザーに親切なメンテナンス画面のデザイン

最後に、メンテナンス画面のデザインについて考えてみましょう。SEO対策も大切ですが、画面を見るのは「人」です。訪問してくれたユーザーをがっかりさせない、親切な画面作りを心がけたいですね。
メンテナンスの終了予定時刻をわかりやすく明記する
ユーザーが一番知りたいのは「いつ使えるようになるの?」という点です。「只今メンテナンス中です」だけでは、1時間後なのか明日なのか分からず、不安を与えてしまいます。
「2023年〇月〇日 10:00 〜 12:00(予定)」のように、終了予定時刻を明確に記載しましょう。これだけでユーザーは「じゃあ、お昼休みにまた見てみよう」と、再訪問の予定を立てやすくなります。
お急ぎのユーザー向けに問い合わせ先を掲載する
ECサイトやサービスサイトの場合、メンテナンス中にお客様が急ぎの用事で連絡を取りたいケースもあるでしょう。
そんな時のために、電話番号やメールアドレス、あるいはTwitter(X)などのSNSアカウントへのリンクを掲載しておくと親切です。「お急ぎの方はこちらへ」という一言があるだけで、信頼感を損なわずに済みます。ユーザーを迷子にさせない配慮が大切ですね。
ブランドイメージを損なわないデザインにする
メンテナンス画面だからといって、無機質な白い背景に黒い文字だけである必要はありません。サイトのロゴを表示したり、ブランドカラーを使ったりして、普段のサイトの雰囲気を感じられるデザインにしましょう。
「あ、間違ったサイトに来ちゃったかな?」という誤解を防げますし、ユーモアのあるイラストやメッセージを添えることで、「工事中も楽しませてくれるサイトだな」と好印象を持ってもらえるかもしれませんよ。
まとめ

いかがでしたか?「503 メンテナンス」の設定は、サイトのSEO評価を守るための大切な防波堤です。
一時的な停止であることを検索エンジンに正しく伝えることで、リニューアル後もスムーズに運営を再開できます。
- 503ステータスコードを必ず返す
- 404や200と混同しない
- ユーザーにも親切な案内画面を用意する
これらのポイントを押さえておけば、もうメンテナンスも怖くありません。手順をしっかり確認して、安全で確実なサイトメンテナンスを行ってくださいね。あなたのサイトがより素敵に生まれ変わることを応援しています!
503 メンテナンスについてよくある質問

サイトのメンテナンスや503エラーに関して、よく寄せられる質問をまとめました。作業前の疑問解消に役立ててください。
- Q. 503設定をしないとどうなりますか?
- A. 検索エンジンがサイトの消失と判断し、検索順位が下がったり、インデックスから削除されたりするリスクがあります。
- Q. WordPressでの設定方法は?
- A. 「WP Maintenance Mode」などのプラグインを使用するのが最も簡単で、初心者の方におすすめです。
- Q. メンテナンス期間の目安は?
- A. 数時間から数日程度が望ましいです。1週間を超えるような長期メンテナンスはSEOへの影響が出やすくなります。
- Q. 503と500エラーの違いは?
- A. 503は「一時的な過負荷やメンテナンス」ですが、500は「サーバー内部のエラー(プログラムミスなど)」を示します。
- Q. 特定のページだけメンテナンス中にできますか?
- A. はい、.htaccessの設定で特定のURLやディレクトリのみを対象に503を返すよう記述することが可能です。


