Googleサーチコンソールの管理画面を開いて「平均掲載順位」のグラフを目にしたとき、「この数字って結局、良いの?悪いの?」と迷ってしまうことはありませんか?
数字が変動するたびに不安になったり、どう判断していいか分からなかったりするのは、Web担当者やブログ運営者なら誰もが通る道です。
実はこの「平均掲載順位」、単なるランキングの平均値というだけでなく、Webサイトの健康状態や、次に打つべき改善策を教えてくれる非常に重要な指標なのです。
この記事では、平均掲載順位の正しい見方や計算の仕組みから、順位を上げてより多くのアクセスを集めるための具体的なステップまで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
数字の意味をしっかりと理解して、あなたのサイトをより多くの人に届けるための第一歩を一緒に踏み出しましょう。
このページに書いてあること
Googleサーチコンソールの「平均掲載順位」とは

Googleサーチコンソールの「検索パフォーマンス」レポートには、表示回数やクリック数など重要な指標が並んでいますが、その中でも「平均掲載順位」はサイトの実力を測るバロメーターと言えます。まずは、この数字が具体的に何を表しているのか、その基本をしっかり押さえておきましょう。
検索結果における順位の平均値を表す指標
平均掲載順位とは、特定の期間中にユーザーがGoogle検索を行った際、あなたのWebサイトが検索結果の「何番目」に表示されたか、その平均値を表す指標です。
例えば、あるキーワードで1位に表示され、別のキーワードでは9位に表示された場合、単純計算で平均は5位となります。ただし、実際には表示された回数なども加味されるため、サイト全体の傾向を掴むための「目安」として捉えるのがおすすめです。この数字が小さくなる(1位に近づく)ほど、検索ユーザーの目に留まりやすくなっていると言えます。
掲載順位が決まる仕組みとカウント方法
Googleの検索結果には、通常のWebページへのリンク(オーガニック検索枠)以外にも、広告枠や地図、画像枠などが表示されることがあります。サーチコンソールにおける順位は、基本的にオーガニック検索枠のリンクを上から数えた順番で決まります。
もし、同じ検索結果画面にあなたのサイトから複数のページが表示された場合は、最も上位にあるリンクの順位がその検索における掲載順位として採用されます。2番目以降のリンク順位は、この場合のカウントには含まれません。
平均掲載順位の計算方法
平均掲載順位の計算は、単純に順位を足して割るだけではありません。「表示された回数」がベースになっています。計算式を簡単に説明すると、以下のようになります。
(各検索での掲載順位の合計) ÷ (検索結果に表示された回数の合計)
注意したいのは、検索結果に一度も表示されなかった(ユーザーの目に触れなかった)場合は、計算に含まれないという点です。つまり、誰かが検索してあなたのサイトが画面に現れたときだけの順位を集計したものが、ここに表示されているのです。
平均掲載順位の目安とクリック率(CTR)の関係
の関係/平均掲載順位の目安とクリック率(CTR)の関係.jpg?_i=AA)
「平均掲載順位が20位だったけれど、これって良い数字なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、検索順位と「どれくらいクリックされるか(CTR)」には密接な関係があります。ここでは、目指すべき順位の目安について解説します。
検索順位1位と10位でのクリック率の違い
検索順位が1つ違うだけで、サイトへのアクセス数は大きく変わります。一般的に、検索順位1位のクリック率は13%〜30%程度と言われていますが、順位が下がるにつれて急激に低下し、10位(1ページ目の最下部付近)になると1%〜2%程度まで落ち込むことが多いです。
- 1位〜3位: 多くのユーザーがクリックする「一等地」
- 4位〜10位: 比較検討するユーザーが見てくれる範囲
- 11位以下: ほとんどクリックされない(2ページ目以降)
このように、まずは1ページ目に入ることが、アクセスを増やすための大きな分岐点となります。
SEO対策で目指すべき順位の目安
Webサイトを運営する上で、最初に目指すべき目安は「平均掲載順位10位以内」です。これは、多くのキーワードで検索結果の1ページ目に表示されている状態を意味します。
もちろん、すべてのキーワードで1位を取るのは現実的ではありません。まずは10位以内を安定させ、そこから特に重要なキーワード(収益につながりやすいページなど)について、トップ3入りを目指して改善を重ねていくのが王道のステップです。
指名検索と一般キーワードでの数値の違い
平均掲載順位を見るときは、「どんな言葉で検索されたか」を区別することが大切です。
- 指名検索(ブランド名など): 会社名やサイト名での検索。競合がいないため、通常は1位になります。
- 一般キーワード: 「SEOとは」「平均掲載順位 目安」など。競合が多く、順位変動も激しいため、10位〜30位程度からスタートすることも珍しくありません。
もしサイト全体の平均順位が良くても、それが指名検索ばかりであれば、新規ユーザーを獲得する力はまだ弱いかもしれません。両者を分けて分析してみましょう。
サーチコンソールで平均掲載順位を確認する手順

理屈がわかったところで、実際にGoogleサーチコンソールの画面を操作して、自分のサイトの順位を確認してみましょう。全体を見るだけでなく、ページ別やキーワード別に細かく見ることで、改善のヒントが見つかります。
サイト全体の平均順位を確認する
まずはサイト全体の健康診断です。サーチコンソールにログインし、左側のメニューから「検索パフォーマンス」をクリックします。
画面上部に表示されるグラフの上に、「合計クリック数」「合計表示回数」「平均CTR」「平均掲載順位」という4つのパネルがあります。ここで「平均掲載順位」をクリックして色を付け(有効化し)ましょう。すると、グラフと下の表に順位のデータが表示されます。これがサイト全体の平均値です。
キーワード(クエリ)ごとの順位を確認する
次に、ユーザーがどんな言葉で検索したときに何位にいるかを確認します。画面下の表にある「クエリ」タブを見てみましょう。
ここには、検索されたキーワード(クエリ)が一覧で並んでいます。リストの右端にある「掲載順位」の列を見ることで、「このキーワードでは1位だけど、あのキーワードでは25位だな」といった具体的な状況が把握できます。順位順に並べ替えることも可能です。
ページごとの順位を確認する
どの記事がGoogleに評価されているかを知るには、「ページ」タブに切り替えます。
サイト内の各ページURLが一覧表示され、それぞれの平均掲載順位が確認できます。「力を入れて書いた記事なのに順位が低い」「意外なページが上位に来ている」といった発見があるはずです。評価が高いページと低いページを比較することで、サイト運営のヒントが得られます。
特定ページの流入キーワード順位を確認する
特定のページが「どのキーワードで」評価されているか深掘りしてみましょう。
- 「ページ」タブで分析したいURLをクリックします。
- フィルタが適用された状態で、再び「クエリ」タブに戻ります。
こうすることで、その特定のページだけに絞った検索キーワードと順位が表示されます。「意図したキーワードで上位表示できているか」を確認するのに非常に便利な機能です。
期間を指定して順位の推移を比較する
施策の効果を確認するには、過去のデータと比較するのが一番です。
画面上部の日付が表示されている部分(例:過去3か月間)をクリックし、「比較」タブを選択します。「過去3か月間」と「前の期間」などを選んで適用すると、順位が上がったのか下がったのか、その変化をグラフと表で比較できます。リライトなどの改善を行った後に必ずチェックしたい項目です。
平均掲載順位を上げるための具体的な改善施策
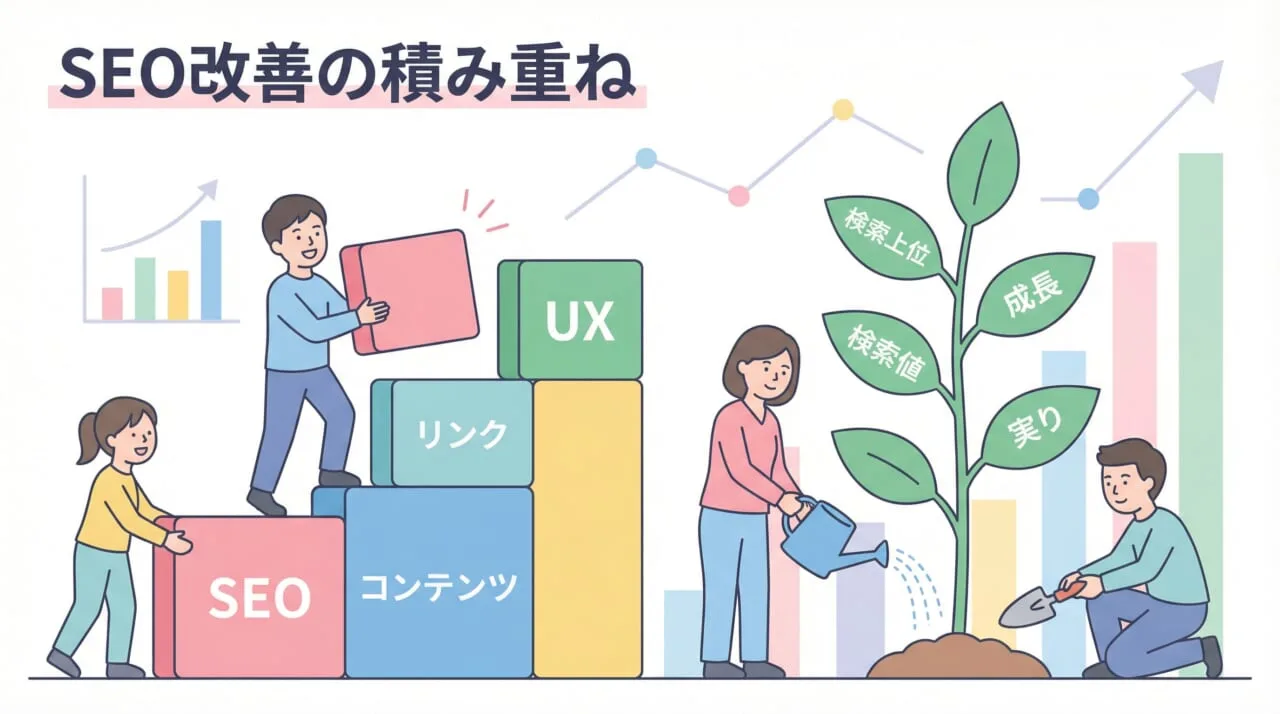
現状の順位が把握できたら、次はいよいよ順位を上げるためのアクションです。SEOは魔法のような裏技があるわけではありませんが、基本に忠実な改善を積み重ねることで、確実に成果が出てきます。ここでは今日からできる具体的な施策をご紹介します。
順位が伸び悩んでいる原因を分析する
やみくもに修正する前に、まずは「なぜ順位が上がらないのか」を考えましょう。対象のキーワードで実際にGoogle検索を行い、上位表示されている競合サイト(1位〜10位)をチェックしてみてください。
- 競合サイトにあって、自分のサイトにない情報は何か?
- 競合の方が図解や体験談が豊富ではないか?
- ページの読み込み速度や見やすさはどうか?
自分に足りない要素を見つけることが、改善のスタートラインです。
ユーザーの検索意図に合わせて記事をリライトする
SEOの本質は「ユーザーの悩みを解決すること」です。順位が低い記事は、ユーザーが知りたい情報(検索意図)を十分に満たしていない可能性があります。
例えば「平均掲載順位 目安」と検索する人は、単なる数字だけでなく「自分のサイトが正常かどうか安心したい」という意図があるかもしれません。そうした深層心理を想像し、答えとなる情報を網羅的に、かつ分かりやすく追記・修正(リライト)しましょう。
クリックされやすいタイトルやディスクリプションに修正する
直接的な順位決定要因ではありませんが、クリック率(CTR)を高めることはSEOにおいて非常に重要です。検索結果に表示されたとき、ついクリックしたくなるようなタイトルや説明文(メタディスクリプション)になっていますか?
- 具体的な数字を入れる(例:5つの改善策)
- ターゲットを明記する(例:初心者向け)
- ベネフィットを伝える(例:順位アップの秘訣)
これらを意識して修正することで、流入が増え、結果的に「ユーザーに支持されているページ」として順位が向上することが期待できます。
関連性の高いページ同士を内部リンクで繋ぐ
サイト内で関連する記事同士をリンクで繋ぐ「内部リンク」は、SEOの基本テクニックです。
例えば、この記事から「SEOの基礎知識」の記事へリンクを貼ることで、読者はより深く学べますし、Googleのクローラー(巡回ロボット)もサイト内をスムーズに移動できるようになります。関連性の高いページ同士を適切に繋ぐことで、サイト全体の専門性と評価を高めることができます。
質の低いコンテンツを見直して整理する
「記事数は多い方が良い」と思われがちですが、質の低いページが大量にあると、サイト全体の評価足を引っ張ることがあります。
- 内容が薄く、誰にも読まれていないページ
- 情報が古すぎて役に立たないページ
- 他のページと内容が重複しているページ
これらは思い切って削除するか、関連する他の記事に統合(リダイレクト)して整理しましょう。サイトをスリム化することで、重要なページに評価を集中させることができます。
平均掲載順位を見る際の注意点とよくある誤解

平均掲載順位は便利な指標ですが、数字の裏側にはいくつかの「落とし穴」もあります。数字だけを見て一喜一憂しないよう、データの特性やよくある誤解について知っておくことが大切です。
自分が検索した順位とサーチコンソールの順位が違う理由
「サーチコンソールでは5位なのに、自分のスマホで検索したら10位だった」という経験はありませんか?これはGoogleが「パーソナライズド検索」を行っているためです。
Googleは、検索する人の位置情報や過去の検索履歴に合わせて、最適な結果を表示し分けています。あなたがよく見る自分のサイトは、あなたに対してだけ上位に表示されている可能性もあります。正確な順位を知るには、必ずサーチコンソールのデータや、シークレットモードでの検索結果を参考にしましょう。
画像検索やマップ枠も順位に含まれる場合がある
掲載順位には、通常のテキストリンクだけでなく、画像検索枠やGoogleマップ枠(ローカルパック)などが含まれる場合があります。
例えば、画像検索結果の一部として表示された場合、順位としてはカウントされますが、通常の検索結果よりもクリックされる確率は低い傾向にあります。「順位は良いのにクリック数が少ない」という場合は、こうした特殊な枠に表示されていないか確認してみると良いでしょう。
平均掲載順位が下がっても流入数が増えるケース
「平均順位が下がった!大変だ!」と焦る前に、流入数(クリック数)を確認してください。実は、順位が下がっても流入数が増えているケースがあります。
これは、新しい記事を追加した際によく起こります。例えば、これまで圏外だった多くのキーワードで50位や60位にランクインし始めると、分母が増えるため「平均」順位は下がります。しかし、これはサイトの露出が増えたというポジティブなサインです。平均値だけでなく、表示回数やクリック数の推移もセットで見ることが重要です。
データに「-(ハイフン)」が表示される理由
Google Search Console(サーチコンソール)などのレポートを確認していると、「平均掲載順位」の項目に数字ではなく「-(ハイフン)」が表示されることがありますよね。これは、指定した期間内にそのキーワードで、Webサイトが検索結果に一度も表示されなかったことを意味しているケースが多いんです。
検索順位が圏外でユーザーの目に留まらなかったり、そもそもそのキーワードで検索された回数が少なかったりする可能性が考えられます。順位を計算するためのデータが足りていない状態と言えるでしょう。まずはコンテンツを充実させて、検索結果にしっかりと表示されることを目指してみてください。
まとめ

今回は、Googleサーチコンソールの「平均掲載順位」について、その意味から具体的な改善策まで解説してきました。
平均掲載順位は、単なる数字のランキングではなく、ユーザーの検索意図に応えられているかを測る大切な指標です。
まずは「10位以内(1ページ目)」を目指し、記事のリライトや内部リンクの設置など、できることから一つずつ取り組んでみてください。
SEOに近道はありませんが、ユーザーにとって有益な情報を発信し続ければ、必ず数字はついてきます。
焦らずじっくりと、サイトを育てていきましょう。
平均掲載順位についてよくある質問

最後に、平均掲載順位に関してよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。疑問を解消して、スッキリした状態でサイト運営に取り組みましょう。
- Q. 平均掲載順位は毎日チェックすべきですか?
- A. 毎日のチェックは必須ではありませんが、大きな変動に気づくために週に1回程度は確認することをおすすめします。記事をリライトした直後などは、こまめに見て効果を測定すると良いでしょう。
- Q. 順位が急に大きく下がってしまいました。どうすればいいですか?
- A. まずは落ち着いて原因を探りましょう。Googleのアルゴリズムアップデートの影響や、サイトの技術的なエラー、あるいは競合サイトの出現などが考えられます。一時的な変動の可能性もあるため、数日間様子を見てから対策を検討しても遅くはありません。
- Q. モバイル(スマホ)とPCで順位は違いますか?
- A. はい、異なります。Googleは「モバイルファーストインデックス」を導入しており、スマホでの見やすさや表示速度が評価に大きく影響します。サーチコンソールではデバイス別の順位も確認できるので、スマホでの順位を優先的にチェックしましょう。
- Q. 新しい記事を書きましたが、順位がつきません。なぜですか?
- A. 公開直後の記事は、Googleに認識(インデックス)されるまでに時間がかかることがあります。数日から数週間かかることも珍しくありません。まずはサーチコンソールの「URL検査」ツールを使って、インデックス登録をリクエストしてみましょう。
- Q. 平均掲載順位の数字が、他のSEOツールの数字と合いません。
- A. 計測方法やデータの取得タイミングが異なるため、ツール間で数字が完全に一致することは稀です。サーチコンソールは実際の検索データに基づいているため、最も信頼できる「一次情報」として扱うのがおすすめです。


