「Webサイトへのアクセスはあるのに、なぜか問い合わせが増えない…」
「広告費をかけているのに、成果につながらず焦っている」
Web担当者として成果を求められる中で、このようなお悩みを抱えていませんか?一生懸命集客しても、最後の「申し込み」や「購入」に至らなければ、ビジネスとしてのゴールは達成できませんよね。
そこで重要になるのが「CV(コンバージョン)改善」です。サイトのちょっとしたボタンの色や、文章の言い回しを変えるだけで、成果が劇的に変わることも珍しくありません。
この記事では、Webマーケティング初心者の方に向けて、CVの基礎知識から、今日からすぐに実践できる具体的な改善テクニックまでを優しく解説します。専門用語もわかりやすく説明しますので、ぜひ最後まで読んで、サイトの成果アップに役立ててくださいね。一緒に「売れるサイト」を目指しましょう!
このページに書いてあること
WebマーケティングにおけるCV(コンバージョン)とは
とは/WebマーケティングにおけるCV(コンバージョン)とは.jpg?_i=AA)
Webマーケティングの世界では、頻繁に「CV」という言葉が飛び交います。まずはこの言葉の意味を正しく理解することから始めましょう。基礎をしっかり固めることが、後の改善施策をスムーズにする第一歩です。ここでは、言葉の定義から計算式まで、やさしく解説しますね。
ビジネスの成果となるCVの意味と定義
CVとは、「Conversion(コンバージョン)」の略で、日本語では「転換」や「変換」を意味します。Webマーケティングにおいては、Webサイトを訪れたユーザーが、サイト運営者の設定した「最終的な成果」となる行動を起こすことを指します。
例えば、商品を購入したり、資料請求をしたりすることがこれに当たります。「cv.」と略記されることもありますが、基本的には「成果」そのものだと捉えてください。単なる閲覧数ではなく、ビジネスに直結する大切なゴール地点なんですよ。
サイトの目的によって異なるCVの種類
「成果」と一口に言っても、サイトの目的によってCVの形はさまざまです。あなたのサイトのゴールはどこにあるでしょうか?
- ECサイト(通販): 商品の購入、カート追加
- BtoBサイト(企業向け): 資料請求、お問い合わせ、見積もり依頼
- 採用サイト: エントリー、説明会予約
- メディアサイト: メルマガ登録、会員登録
このように、「ユーザーに何をしてほしいか」によってCVの種類は変わります。まずは自社サイトのCVを明確に定義することが大切ですね。
CVとCVRの違いとは?計算式と関係性
よく似た言葉に「CVR(コンバージョンレート)」があります。「cv cvr 違い」と検索されることも多いですが、この2つの関係性はとても重要です。
- CV(コンバージョン数): 成果が発生した「回数」(例:10件の申し込み)
- CVR(コンバージョン率): 訪問者全体のうち、成果に至った「割合」
計算式は以下のようになります。
CVR(%) = CV数 ÷ セッション数(訪問数) × 100
例えば、100人がサイトに来て1人が購入したら、CVは1、CVRは1%です。「cv%」と表記されることもありますね。CVRを高めることが、効率的なサイト運営の鍵となります。
広告運用におけるCVの考え方
Web広告を出稿している場合、「cv広告」や「cvとは 広告」という文脈で考える必要があります。広告運用では、広告をクリックしてサイトに来たユーザーが、どれだけCVに至ったかが費用の対効果(コスパ)を判断する基準になります。
広告費をかけて集客してもCVが発生しなければ赤字になってしまいますよね。そのため、広告の管理画面では「CPA(獲得単価)」や「ROAS(広告費用対効果)」といった指標とあわせて、常にCV数をチェックし続ける必要があるのです。
なぜWebサイトにCV改善が必要なのか
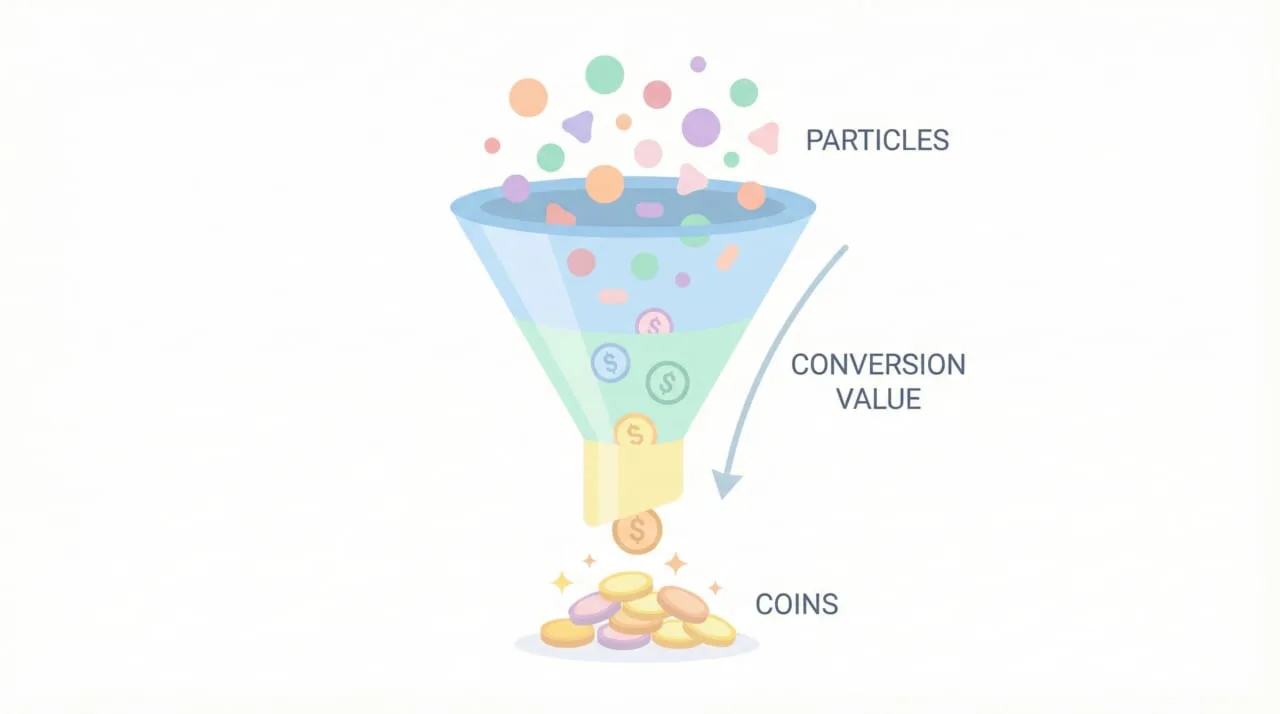
「アクセスさえ集めれば売上は上がるはず」と思っていませんか?実は、それだけでは不十分なんです。ここでは、なぜWebサイトにおいて集客だけでなく「CV改善」に力を入れるべきなのか、その理由をビジネス視点で掘り下げてみましょう。
アクセス数だけでは売上が上がらない理由
想像してみてください。底に穴の空いたバケツに、一生懸命水を注いでいる状態を。これでは、いくら水を注いでも(アクセスを集めても)、水はどんどん漏れてしまい、バケツはいっぱいになりませんよね。
Webサイトも同じです。サイトの中身が使いにくかったり魅力的でなかったりすると、せっかく訪れたユーザーは何もせずに帰ってしまいます。アクセス数を増やす前に、まず「穴をふさぐ(CV率を高める)」ことが、売上アップへの近道なのです。
広告費の無駄を削減して利益率を高める
CVR(コンバージョン率)が上がると、同じアクセス数でも成果件数が増えます。これはつまり、広告費や集客コストを変えずに、売上や利益を増やせるということです。
例えば、CVRが1%から2%に改善されれば、成果は2倍になります。新たに広告費を追加することなく成果を倍増させられるので、結果として利益率が大幅に向上します。無駄なコストを削減し、筋肉質な経営体質を作るためにも、CV改善は欠かせません。
顧客獲得単価(CPA)を下げて効率化する
Webマーケティングでは「CPA(Cost Per Action:顧客獲得単価)」という指標が重要視されます。これは、1件の成果(CV)を獲得するのにかかった費用のことです。
CV改善を行ってCVRが高まれば、少ないアクセス数でも多くの成果が得られるため、必然的にCPAは下がります。
- 改善前: 1万円の広告費で1件獲得(CPA 10,000円)
- 改善後: 1万円の広告費で2件獲得(CPA 5,000円)
このように獲得効率が良くなれば、浮いた予算を別の施策に回すこともできるようになりますね。
成果を出すためのCV分析と現状把握

闇雲にサイトを変更しても、なかなか成果は出ません。まずは「どこが悪いのか」を正しく知る必要があります。お医者さんが診察してから治療するように、Webサイトも「cv分析」を行って現状を把握しましょう。具体的な分析手法をご紹介します。
Googleアナリティクスで現在の数値を計測する
まずは、Googleアナリティクス(GA4)などの解析ツールを使って、現在の実力を数値化しましょう。感覚で「なんとなく少ない」と思うのではなく、データとして捉えることが大切です。
- 現在の月間CV数とCVR
- どのチャネル(検索、SNS、広告)からのCVが多いか
- スマホとPC、どちらのCVRが高いか
これらの基本データを確認するだけでも、改善のヒントが見えてくるはずです。まずは現状の「健康診断」から始めてみてください。
ユーザーが離脱しているページを特定する
ユーザーはサイトのどのページで「やっぱりやめた」と帰ってしまっているのでしょうか?特定のページで多くの人が離脱しているなら、そこに大きな問題がある可能性があります。
特に注目したいのは、申し込みフォームやカートページでの離脱です。あと一歩で購入という段階で離脱している場合、入力フォームの使い勝手やエラー表示に原因があることが多いです。離脱率が高いページを特定し、優先的に修正リストに加えましょう。
ヒートマップツールで熟読箇所を可視化する
「ヒートマップツール」を使うと、ユーザーの行動を色で可視化できます。サーモグラフィのように、よく見られている場所は赤く、見られていない場所は青く表示されるツールです。
- 熟読エリア: ユーザーが興味を持って読んでいる箇所
- クリック箇所: リンクがないのにクリックされている画像や文字
- スクロール到達率: ページのどこまで読まれているか
これらを知ることで、「重要なボタンが見られていない」「この文章は読み飛ばされている」といった具体的な課題が浮き彫りになります。
競合サイトと比較して不足要素を洗い出す
自社サイトだけでなく、競合他社のサイトを分析することも非常に有効です。「コンバージョン cv」に至るまでの流れを実際に体験してみましょう。
- 競合はどんな訴求をしているか?
- 申し込みボタンのデザインや文言は?
- 入力フォームの項目数は?
競合にあって自社にない要素や、逆に自社が勝っている部分を洗い出します。他社の良いところを取り入れつつ、自社独自の強みをアピールする方法を考えてみましょう。
すぐに実践できるCV改善の施策【デザイン・導線編】
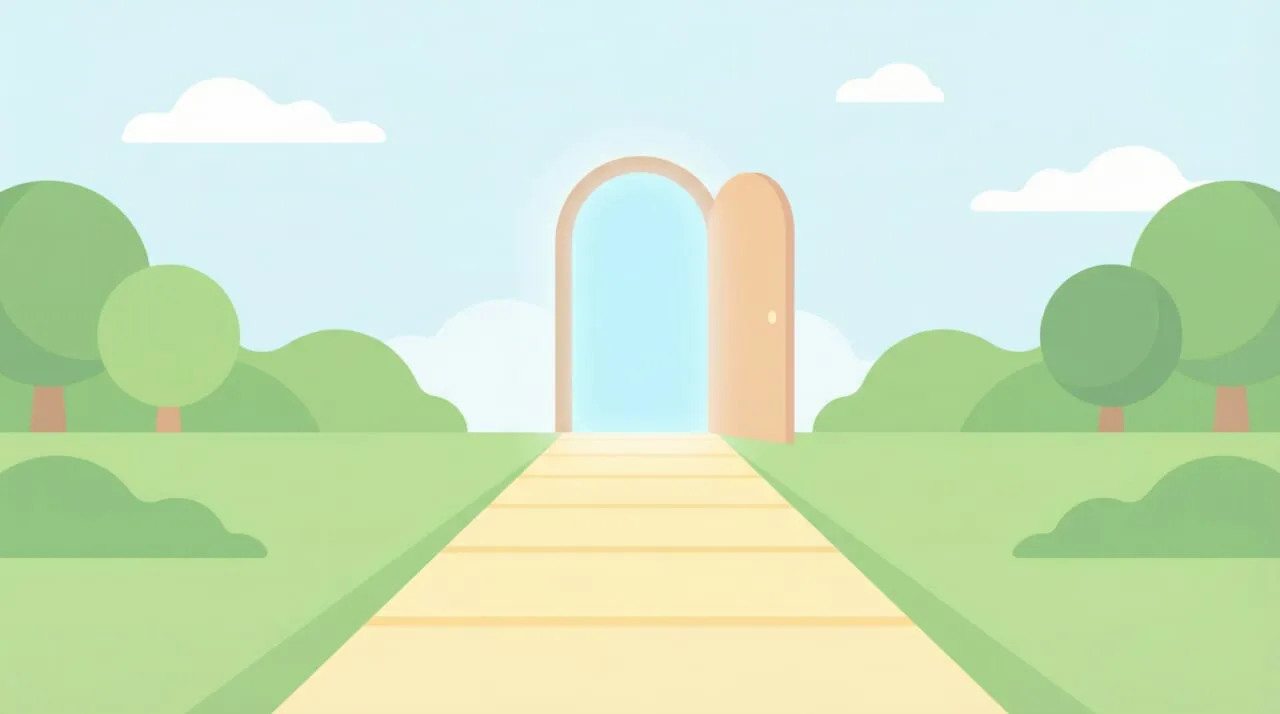
現状が把握できたら、いよいよ具体的な改善アクションに移りましょう。まずは、デザインやページの導線など、見た目や使い勝手に関する部分から。「これならすぐに直せそう!」と思えるポイントをまとめました。
ファーストビューで何のサイトか一目で伝える
Webサイトを訪れたユーザーは、最初の3秒で「このサイトは自分に関係があるか」を判断すると言われています。これを「3秒ルール」と呼びます。
ページを開いた瞬間に目に入る「ファーストビュー」で、以下の情報を明確に伝えましょう。
- 誰のためのサービスか
- どんなメリットがあるか
- 実績や権威性(No.1など)
ここが曖昧だと、ユーザーはすぐに「戻る」ボタンを押してしまいます。キャッチコピーとメイン画像で、一瞬で心を掴む工夫が必要です。
CTAボタン(申し込みボタン)を目立つ色にする
申し込みや購入へ進むためのボタンを「CTA(Call To Action)ボタン」と呼びます。このボタンが背景に馴染んでしまっていませんか?
CTAボタンは、サイト内で最も目立つ色(アクセントカラー)を使いましょう。一般的には、緑やオレンジ、赤などがクリックされやすいと言われていますが、サイト全体の配色とのバランスで「一番目立つ色」を選ぶのが正解です。影をつけて立体的にし、「押せそう」に見せるのも効果的ですよ。
ボタンのテキストをクリックしたくなる文言に変える
ボタンのテキストが単なる「送信」や「申し込み」になっていませんか?これではユーザーの意欲を掻き立てられません。ユーザーが得られるメリットや、ハードルの低さを伝える「マイクロコピー」を工夫しましょう。
- 悪い例:「登録する」
- 良い例:「1分で完了! 無料で登録する」
- 良い例:「今すぐ カタログを見る」
行動した後の未来を想像させる言葉や、簡単さをアピールする言葉を添えるだけで、クリック率は驚くほど変わります。
ページ内のボタン設置数を増やして機会を逃さない
「申し込みたい」と思った瞬間にボタンが見当たらないと、ユーザーの熱は冷めてしまいます。ボタンはページの最下部だけでなく、適切なタイミングで複数箇所に設置しましょう。
- ファーストビュー直下
- メリットを説明した後
- お客様の声の後
- ページの最下部
- 追従するフッター(固定フッター)
特にスマートフォンでは、画面下部に常にボタンが表示される「追従ボタン」が非常に効果的です。「いつでも申し込める」状態を作っておくことが大切です。
スマートフォンでの操作性と見やすさを最優先する
今や多くのサイトで、PCよりもスマートフォンからのアクセスが多くなっています。PCでの見た目は綺麗でも、スマホで見ると文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりしていませんか?
- 指でタップしやすいボタンサイズにする
- 文字サイズを読みやすく調整する
- 画像の配置を縦並びに見やすくする
「モバイルファースト」の考え方で、まずはスマホでの使いやすさを最優先に改善しましょう。スマホでのCVR改善が、全体の成果を大きく引き上げます。
ページの表示速度を改善して離脱を防ぐ
ページの読み込みに3秒以上かかると、半数以上のユーザーが離脱するというデータもあります。表示速度の遅さは致命的です。
- 画像のファイルサイズを圧縮する
- 不要なアニメーションを削除する
- サーバー環境を見直す
Googleの「PageSpeed Insights」などのツールを使って速度を計測し、改善点を見つけましょう。サクサク動くサイトは、それだけでユーザーに好印象を与え、CVへの道をスムーズにします。
グローバルナビゲーションを整理して迷わせない
サイトの上部にあるメニュー(グローバルナビゲーション)が複雑すぎると、ユーザーは迷子になってしまいます。「c/v」を最大化するためには、迷わせないことが鉄則です。
項目を詰め込みすぎず、ユーザーが本当に知りたい情報(料金、事例、会社概要など)に絞って整理しましょう。「お問い合わせ」や「資料請求」などのCVにつながるメニューは、色を変えて目立たせるのもおすすめです。シンプルで直感的なナビゲーションを目指してください。
ユーザーの心を掴むCV改善の施策【コンテンツ・文章編】

デザインが整ったら、次は中身の「コンテンツ」です。ユーザーの感情に訴えかけ、信頼を勝ち取ることで、CVへのハードルを下げることができます。言葉の力を使って、ユーザーの背中を優しく押してあげましょう。
ターゲットの悩みや不安に共感する文章を入れる
人は「自分のことを分かってくれている」と感じると、その相手を信頼します。まずはターゲットとなるユーザーが抱えている悩みや不安を言語化し、共感を示しましょう。
「〇〇でお困りではありませんか?」
「初めてで不安なことも多いですよね」
このように寄り添う言葉を投げかけることで、「ここは私のためのサイトだ」と認識してもらえます。共感から始まるコミュニケーションは、その後の提案を受け入れてもらいやすくする土台となります。
導入実績やお客様の声で信頼性を高める
初めて利用するサービスには、誰しも警戒心を持つものです。「本当に大丈夫かな?」という不安を払拭するために、第三者の声を掲載しましょう。
- 導入実績: 「〇〇社に導入いただきました」
- お客様の声: 写真付きや手書きの感想は特に効果的
- 事例紹介: 具体的なBefore/Afterのストーリー
「みんなが使っているなら安心だ」という心理(社会的証明)が働き、申し込みへの心理的ハードルがぐっと下がります。
権威あるデータや受賞歴で説得力を強める
「自称すごい」よりも、客観的な評価の方が説得力があります。権威性をアピールできる要素があれば、積極的に掲載しましょう。
- 受賞歴: 「〇〇賞 受賞」「満足度No.1」
- メディア掲載: 「テレビ〇〇で紹介されました」
- 有資格者の監修: 「医師監修」「専門家推奨」
- 具体的な数値データ: 「リピート率98%」「累計10万部突破」
これらの情報は、ユーザーに「失敗したくない」という心理的な安心感を与え、CV(コンバージョン)への決断を後押しします。
期間限定や数量限定で「今すぐやる理由」を作る
人は「いつでもできる」と思うと、行動を先延ばしにしてしまいがちです。その結果、忘れ去られてしまうことも…。そこで、「今すぐやる理由」を作ってあげることが大切です。
- 期間限定: 「今月末までのキャンペーン」
- 数量限定: 「先着10名様限定」
- 特典: 「今なら〇〇をプレゼント」
このような限定性や緊急性をアピールすることで、「損をしたくない」という心理が働き、その場での申し込みを促すことができます。
不安を取り除く「よくある質問」を充実させる
申し込み直前にふと浮かぶ疑問や不安。これが解消されないと、ユーザーは離脱してしまいます。「よくある質問(FAQ)」を充実させることで、これらの不安を先回りして解消しましょう。
- 「契約期間の縛りはありますか?」
- 「初心者でも使えますか?」
- 「解約は簡単にできますか?」
ユーザーが電話やメールで問い合わせる手間を省き、自己解決できるようにすることで、スムーズにCVへ誘導できます。「cvtoha」のような用語の疑問もここで解消してあげると親切ですね。
メリットだけでなくベネフィット(得られる未来)を伝える
商品のスペック(機能)ばかり説明していませんか?ユーザーが本当に知りたいのは、その商品を使った後に「自分がどうなれるか」という未来(ベネフィット)です。
- メリット(機能): 「この掃除機は吸引力が強いです」
- ベネフィット(未来): 「掃除の時間が半分になり、家族とゆっくり過ごせます」
機能の特徴だけでなく、その先にある「素敵な未来」を文章で描くことで、ユーザーの「欲しい!」という感情を強く刺激することができます。
申し込みの壁を取り払うCV改善の施策【入力フォーム編】
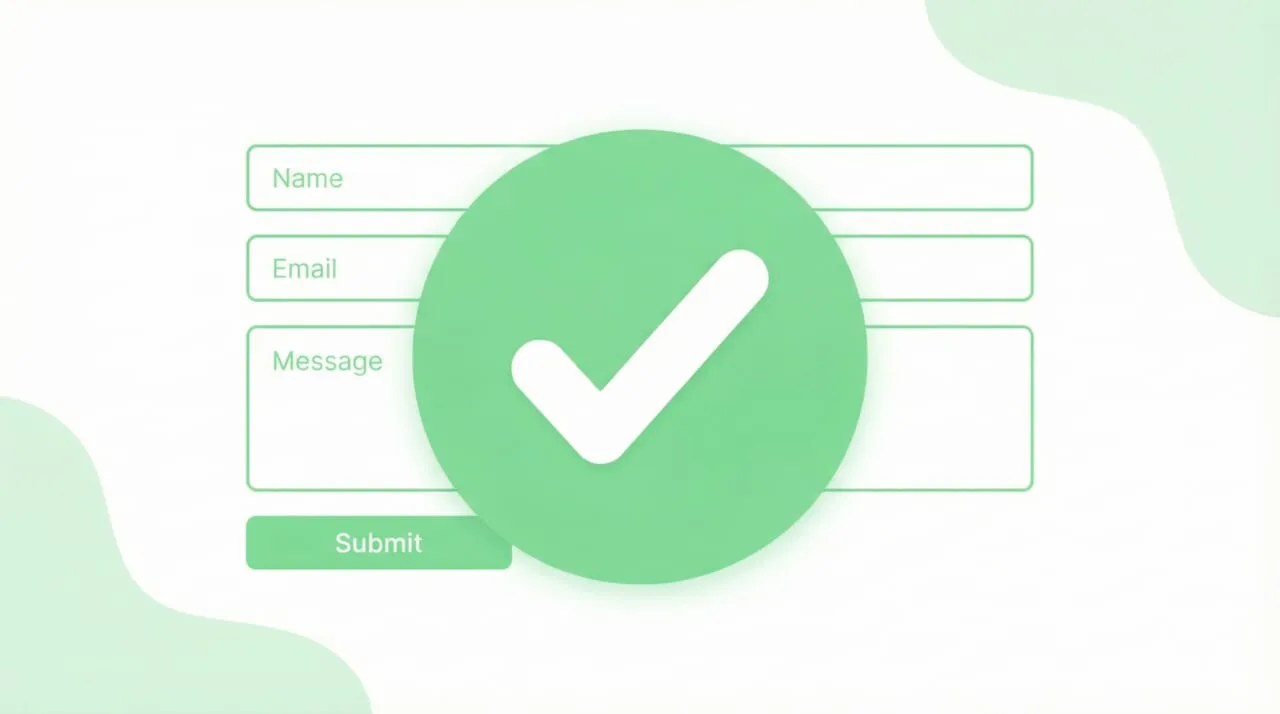
「申し込みボタン」を押した後に待ち受けるのが入力フォームです。実はここが最大の難関。入力が面倒で諦めてしまうユーザーは非常に多いのです。この「入力フォーム最適化(EFO)」こそが、CV改善の即効薬になります。
入力項目を必要最低限まで削る
フォームの入力項目が多いだけで、ユーザーはうんざりしてしまいます。「ふりがな」は本当に必要ですか?「性別」や「FAX番号」は必須ですか?
マーケティングのために情報を集めたい気持ちはわかりますが、CVRを上げるためには「必要最低限」に絞ることが鉄則です。名前、メールアドレス、問い合わせ内容など、どうしても必要な項目以外は思い切って削除するか、任意項目にしましょう。項目が減るだけでCV率が上がるケースは非常に多いですよ。
郵便番号からの住所自動入力機能を導入する
住所入力は特に手間がかかる部分です。郵便番号を入力すると、自動で住所(都道府県や市区町村)が入力される機能を導入しましょう。
これにより、ユーザーの手間が大幅に減るだけでなく、入力ミスも防げます。スマホでの入力は特に大変なので、こうした補助機能があるだけでユーザーのストレスは大きく軽減され、途中離脱を防ぐことができます。
全角・半角の指定など入力制限を緩める
「全角で入力してください」「ハイフンなしで入力してください」といった細かい指定は、ユーザーにとって大きなストレスです。これらが原因でエラーが出ると、イライラして離脱してしまいます。
システム側で全角・半角を自動変換したり、ハイフンの有無に関わらず受け付けたりするように設定しましょう。ユーザーに厳密さを求めるのではなく、システム側で柔軟に対応する姿勢が、CV改善につながります。
必須項目と任意項目を明確にデザインで分ける
どれが必ず入力すべき項目で、どれが書かなくてもいい項目なのか、一目でわかるようにしましょう。
- 必須項目: 赤い「必須」マークを目立つように配置
- 任意項目: グレーの「任意」マーク、または背景色を変える
必須項目と任意項目が混ざっていると、ユーザーは「全部書かなきゃいけないの?」と誤解して心理的負担を感じてしまいます。メリハリのあるデザインで、入力のハードルを下げましょう。
入力例を表示してユーザーを迷わせない
「お問い合わせ内容」などの自由記述欄で、何を書けばいいか迷わせないようにしましょう。入力欄の中に薄い文字(プレースホルダー)で入力例を表示しておくと親切です。
例:「(例)資料請求について」「(例)山田 太郎」
また、「c.v. とは」のような専門用語を使わず、誰にでもわかる言葉で項目名を記載することも大切です。迷わせない工夫が、スムーズな入力を促します。
エラー表示をリアルタイムで分かりやすく出す
全ての項目を入力して送信ボタンを押した後に、「エラーがあります」と返されるのは非常にストレスです。最悪の場合、入力内容が消えてしまうことも…。
エラーがある場合は、入力したその瞬間に「メールアドレスの形式が正しくありません」のようにリアルタイムで表示するようにしましょう。どの項目が間違っているのかをその場で教えることで、修正の手間を最小限に抑えられます。
送信ボタンを押したくなるデザインと文言にする
最後の送信ボタンも気を抜けません。ただの「確認」や「送信」というグレーのボタンではなく、思わず押したくなるようなデザインにしましょう。
- 色:目立つアクセントカラーを使用
- 文言:「同意して確認画面へ進む」「無料で資料を受け取る」
- 動き:マウスを乗せると色が少し変わるなど
さらに、ボタンの近くに「送信しても料金は発生しません」などの安心材料(マイクロコピー)を添えるのも効果的です。最後のひと押しを大切にしましょう。
効果検証を繰り返してCVRを高めるポイント

CV改善は、一度やって終わりではありません。施策を実施したら、必ず結果を検証し、さらに良くしていくプロセスが必要です。ここでは、効率よく改善を続けていくためのポイントをお伝えします。
一度に多くの箇所を変更せず一つずつテストする
「あれもこれも」と一度にたくさんの箇所を変更してしまうと、結果が良くなっても悪くなっても「何が原因だったのか」が分からなくなってしまいます。
「まずはボタンの色を変えてみる」、その結果を確認してから「次はキャッチコピーを変える」というように、変更箇所は一つずつに絞りましょう。地道ですが、この積み重ねが確実なノウハウとして蓄積されていきます。
ABテストを実施してデータを比較検証する
どちらのデザインが良いか迷ったら、「ABテスト」を行いましょう。これは、Aパターン(元のデザイン)とBパターン(変更案)をランダムにユーザーに表示し、どちらのCVRが高かったかを比較する方法です。
「こっちの方が良さそう」という主観ではなく、実際のユーザー行動データに基づいて判断できるため、失敗が少なくなります。Googleオプティマイズなどのツールを使えば、比較的簡単に実施できますよ。
常にユーザー視点に立って使いやすさを追求する
数値やデータを見ることは大切ですが、一番忘れてはいけないのは「画面の向こうにいるのは感情を持った人間である」ということです。
「この表現は不快じゃないか?」「ここで迷わないか?」と、常にユーザーの立場になって考え続けましょう。自分自身でサイトを使ってみたり、身近な人に操作してもらって感想を聞いたりするのも有効です。徹底したユーザー視点こそが、最強のCV改善策になります。
まとめ

いかがでしたか?今回は「cv改善」をテーマに、基礎知識から具体的なテクニックまで幅広くご紹介しました。
CV(コンバージョン)とは、単なる数値ではなく、お客様との「出会い」そのものです。
ボタンの色を変える、フォームを短くする、共感する文章を書く。これらはすべて「お客様にもっと快適に使ってほしい」というおもてなしの心から生まれるものです。
一度にすべてを完璧にする必要はありません。
「今日はボタンの文言を見直してみようかな」
「明日はスマホでの表示を確認してみよう」
そんな小さな一歩からで大丈夫です。
PDCAを回し、テストを繰り返すことで、あなたのサイトは確実に「成果の出るサイト」へと育っていきます。焦らず、ユーザー視点を忘れずに、できることから一つずつ取り組んでみてくださいね。あなたのサイトが、多くのお客様と繋がる素敵な場所になることを応援しています!
cv改善についてよくある質問

Web担当者の方からよくいただく質問をまとめました。改善に取り組む際の参考にしてください。
- CVRの平均はどれくらいですか?
- 業界や商材によって大きく異なりますが、一般的にはECサイトで1〜2%、BtoBの資料請求などで1〜3%程度が目安と言われています。ただし、指名検索が多い場合などは10%を超えることもあります。他社平均にとらわれすぎず、自社の過去データと比較して改善していくことが大切です。
- CV改善の効果はどれくらいの期間で出ますか?
- 施策の内容によりますが、ボタンの変更やフォームの改善などは、変更した直後から数値に変化が現れることが多いです。一方、コンテンツの修正やSEO施策などは効果が出るまで数週間〜数ヶ月かかることもあります。まずは2週間程度データを計測して判断するのがおすすめです。
- アクセス数が少なくてもCV改善はすべきですか?
- はい、すべきです。ただし、月間のアクセス数が極端に少ない(例:数百以下)場合は、統計的な判断が難しいため、まずは集客(SEOや広告)に力を入れるべきフェーズかもしれません。ある程度のアクセス(月間数千〜)がある段階で、CV改善に取り組むと効果が見えやすくなります。
- 「マイクロコンバージョン」とは何ですか?
- 最終的な成果(CV)の手前に設定する中間目標のことです。例えば「購入」が最終CVなら、「カート追加」や「詳細ページ閲覧」「滞在時間○分」などがマイクロコンバージョンになります。CV数が少なすぎて分析できない時に、この指標を使って改善のヒントを探すことができます。
- CV分析におすすめのツールはありますか?
- 基本となるのはGoogleが提供している「Googleアナリティクス(GA4)」と「Googleサーチコンソール」です。これらは無料で使えます。さらに詳しい分析をしたい場合は、「Microsoft Clarity(無料)」などのヒートマップツールを導入すると、ユーザーの動きが視覚的にわかるようになります。


