「自社のWebサイト、今の成果で本当に大丈夫かな?」
「CVR(コンバージョン率)の数字は出たけれど、これが良いのか悪いのか判断できない…」
Webマーケティングを担当し始めたばかりの方や、ECサイトを運営されている方にとって、このようなお悩みはつきものですよね。目標を立てようにも、一般的な基準や相場がわからないと、目指すべきゴールが見えてきません。
実は、CVRの平均値は業界や扱う商材、集客方法によって大きく異なります。単に全体の平均と比べるのではなく、自社の状況に近いデータと比較することが大切なんです。
この記事では、業界別や媒体別、デバイス別の「cvr 平均」データを詳しくご紹介します。さらに、平均より低かった場合の具体的な改善策まで、初心者の方にもわかりやすく解説しますね。自社の数値を客観的に評価して、次のステップへ進むためのヒントにしてください。
このページに書いてあること
CVR(コンバージョン率)とは?計算式と平均の目安
とは?計算式と平均の目安/CVR(コンバージョン率)とは?計算式と平均の目安.jpg?_i=AA)
まずは、基本となる「CVR(コンバージョン率)」の意味や計算方法をおさらいしましょう。基礎をしっかり理解することで、後ほどご紹介するデータの見方も変わります。ここでは、全体的な平均の目安についても触れていきますね。
コンバージョン率(転換率)の基本的な意味と計算方法
CVRとは「Conversion Rate(コンバージョンレート)」の略で、日本語では「コンバージョン率」や「転換率」と呼ばれます。Webサイトを訪れた人のうち、どのくらいの割合が商品購入やお問い合わせといった「成果(コンバージョン)」に至ったかを示す重要な指標です。
計算式はとてもシンプルです。
- CVR(%) = コンバージョン数 ÷ セッション数(訪問数) × 100
例えば、サイトへの訪問数が1,000件で、そのうち10件が購入に至った場合、10 ÷ 1,000 × 100 = 1%
となり、CVRは1%です。
この計算式を覚えておくと、自社のサイトパフォーマンスをいつでもチェックできるようになりますね。
全体的なCVR平均と判断基準となる目安
では、一般的にどれくらいの数値なら「良い」とされるのでしょうか?
全業界・全サイトをひっくるめた全体的なCVR平均は、おおよそ「2%〜3%」程度と言われることが多いです。
ただ、これはあくまで大きな目安にすぎません。例えば、手軽に買える日用品と、検討期間が長い高額なBtoB商材とでは、当然ながら数値は異なります。「cvr平均」を知る際は、この全体平均を頭の片隅に置きつつ、次にご紹介する「業界別」や「媒体別」の詳細なデータと比較することが重要です。
「うちは平均より低いかも…」と焦る前に、まずは自社のカテゴリに近い相場を確認してみましょう。
【業界別】コンバージョン率平均のデータ詳細

ここからは、より具体的な「業界別 コンバージョン率」のデータを見ていきましょう。扱っている商品やサービスの種類によって、ユーザーの決断スピードやハードルが異なるため、平均値にも大きな差が出ます。ご自身の業界に近いものを参考にしてくださいね。
ECサイト(物販)のCVR平均
ECサイト(物販)における「ec cvr 平均」は、扱っている商材の価格帯やジャンルによって幅がありますが、一般的には1%〜3%程度が目安とされています。
- アパレル・雑貨: 比較検討されやすいため、1.5%〜2.5%程度
- 食品・日用品: リピート購入も多く、やや高めの2%〜4%程度
- 家電・家具: 高単価で検討期間が長いため、0.5%〜1.5%程度
「ec コンバージョン率」は、セール時期や季節イベントによっても大きく変動するのが特徴です。まずは2%を目標の一つに設定してみると良いでしょう。
BtoBサービスのCVR平均
企業間取引である「btob cvr平均」は、コンバージョンポイント(成果地点)の設定によって大きく変わります。
- 資料請求・ホワイトペーパーDL: ハードルが低いため、2%〜5%程度と高めに出る傾向があります。
- お問い合わせ・見積もり依頼: 具体的な検討段階に入るため、0.5%〜1.5%程度が相場です。
BtoBでは、即決することは稀で、社内稟議などのプロセスが入ります。「btob cvr」を見る際は、リード(見込み客)獲得を目的にしているのか、商談獲得を目的にしているのかで基準を使い分けることが大切です。
金融・保険業界のコンバージョン率
金融(銀行、証券、ローンなど)や保険業界のコンバージョン率は、他の業界に比べて高めの傾向にあり、3%〜5%、場合によってはそれ以上になることもあります。
これは、ユーザーが「口座を開設したい」「保険を見直したい」という明確な目的を持って検索し、サイトを訪問することが多いためです。ただし、審査が必要なサービスなどでは、申し込み完了までのハードルが高くなるため、数値が下がることもあります。信頼性が何より重視される業界なので、サイトの安心感も数値に影響します。
不動産業界のコンバージョン率
不動産業界(賃貸、売買、リフォームなど)では、人生で一番高い買い物と言われるだけあって、ユーザーは慎重に検討を重ねます。そのためCVRも低くなりそうですが、実際にはどうなのでしょうか。
信頼できる調査データ(WordStream社など)を見ると、不動産業界のCVR 平均は以下のようになっています。
- リスティング広告: 具体的に探している人が多いため、2.47%
- ディスプレイ広告: 広くアピールするため少し下がり、0.80%
以前はもっと低い数値(0.5%〜1.5%程度)で語られることもありましたが、最近の調査ではもう少し高い水準にあるようです。また、賃貸や売買といった種別ごとの詳細な平均データは少ないため、まずはこの全体の数値を参考にすると良いでしょう。
不動産の場合、Webサイトだけで完結せず、まずは「内見予約」や「来店」につなげることがゴールになるケースが多いですよね。そのため、Web上のCVRだけでなく、その後の成約率まで含めてトータルで判断するようにしましょう。
旅行・観光業界のコンバージョン率
旅行・観光業界のコンバージョン率は、2%〜4%程度が平均的な目安です。
旅行は「楽しみ」のための出費であり、写真や口コミを見て気分が盛り上がったタイミングで予約されることが多いため、比較的高めの数値が出やすい傾向にあります。
ただし、季節要因(ゴールデンウィークや年末年始など)や、社会情勢による影響を非常に受けやすい業界でもあります。平均値を見る際は、繁忙期と閑散期を分けて分析することをおすすめします。
教育・人材業界のコンバージョン率
教育(スクール、通信講座)や人材(転職エージェント、求人サイト)業界のコンバージョン率は、流入経路によって差があります。ある調査(WordStream)によると、自然検索から流入した場合のcvr 平均は、教育業界で約3.4%、人材業界で約5.1%となっています。
特に「無料体験レッスン」や「無料カウンセリング」など、金銭的なリスクがないオファーを用意していると、申し込みへのハードルが下がりますよね。こうした工夫をすることで、より高い成果が期待できるでしょう。
一方で、ディスプレイ広告経由の場合などは0.5%〜1.6%程度と、数値が低くなる傾向もあります。いきなり高額な受講料を支払う設定にするよりも、ユーザーさんが最初に踏み出す一歩をどれだけ低くできるかが、大切なポイントになりそうですね。
【媒体・チャネル別】広告やSEOのCVR平均

同じWebサイトでも、ユーザーがどこからやってきたか(流入経路)によって、モチベーションの高さは全然違います。当然、「広告 cvr」や自然検索のCVRにも差が出てきます。ここでは、チャネルごとの平均的な相場を見ていきましょう。
リスティング広告のCVR平均
リスティング広告(検索連動型広告)のCVR平均は、3%〜4%程度と高くなる傾向があります。
これは、ユーザーが自らキーワードを入力して検索しているため、「今すぐ欲しい」「解決したい」という意欲(検索意図)が高いからです。「広告 cvr 平均」の中でも、特に成果に直結しやすい手法と言えますね。指名キーワード(サービス名など)での検索なら、さらに高い数値(10%以上)が出ることも珍しくありません。
ディスプレイ広告・SNS広告のCVR
一方、ディスプレイ広告やSNS広告(Facebook、Instagram、Xなど)のCVRは、0.5%〜1%程度と低めになるのが一般的です。
これらの広告は、ユーザーが何か別のことをしている時(記事を読んでいる、SNSを見ている)に表示されるため、ニーズが顕在化していない「潜在層」へのアプローチが中心になります。そのため、直接的なコンバージョンよりも、まずは認知拡大やクリック数を重視する場合も多いですね。
自然検索(SEO)のコンバージョン率
GoogleやYahoo!などの自然検索(オーガニック検索)経由のコンバージョン率は、2%〜3%程度が平均的な目安です。
ただし、これは「どんなキーワードで上位表示されているか」に大きく左右されます。「〇〇 おすすめ」のような比較検討キーワードならCVRは高くなりますが、「〇〇とは」のような情報収集キーワード(Knowクエリ)ばかりで流入している場合、アクセス数は多くてもCVRは低くなる傾向があります。SEOでは、量だけでなく「質」も重要なんですね。
メルマガ経由のCVR平均
メールマガジン経由のCVR平均は、3%〜5%以上と、非常に高いパフォーマンスを出すことが多いです。
メルマガを受け取っている時点で、すでに一度接点がある「既存顧客」や「ファン」である可能性が高いためです。特に、過去の購入履歴に基づいたおすすめ商品や、会員限定のセール情報は反応が良く、「転換率 平均」を大きく引き上げる要因になります。リピーター育成には欠かせないチャネルですね。
【デバイス別】スマホとPCのCVR相場

最近はスマホで買い物をする人が増えましたが、実はデバイス(端末)によってもCVRの相場は異なります。PCとスマホ、それぞれの特徴を理解して数値を見ることが大切です。
PC(デスクトップ)の平均値
PC(デスクトップ)からのコンバージョン率は、2%〜4%程度と、スマホに比べて高くなる傾向があります。
画面が大きく情報が見やすいため、商品の詳細をじっくり確認したり、複数のサイトをタブで開いて比較検討したりするのに適しているからです。特にBtoB商材や高額な商品は、職場のPCや自宅のPCで落ち着いて申し込み作業を行う人が多いため、PCのCVRが重要視されます。
スマートフォン(モバイル)の平均値
スマートフォン(モバイル)のコンバージョン率は、1%〜2%程度と、PCよりも少し低くなるのが一般的です。
スマホは移動中や隙間時間に手軽に見られる反面、通信環境の影響や、入力フォームの操作のしにくさから、途中で離脱してしまうケースが多いためです。しかし、業界によっては(特に若年層向けのECなど)、スマホ経由のアクセスが8割以上を占めることもあります。スマホのCVR改善は、今のWebマーケティングにおいて最優先課題と言えるでしょう。
自社のCVRが平均より低い場合の改善施策

「自社のCVR、やっぱり平均より低いかも…」と落ち込む必要はありません。原因を見つけて対策すれば、数値は必ず改善できます。ここでは、CVRをアップさせるための代表的な4つの施策をご紹介します。
ターゲットユーザーと流入キーワードの再設計
まず見直したいのが、「集客しているユーザー」と「サイトの内容」が合っているかどうかです。
例えば、「高級 腕時計」を売りたいのに、「安い 時計」というキーワードで集客していませんか?これでは、訪れたユーザーは「思っていたのと違う」と感じてすぐに帰ってしまいます。
ターゲットユーザーが検索しそうなキーワードと、ランディングページ(着地ページ)の内容がマッチしているか、検索意図を再確認してみましょう。質の高い流入を増やすことが、CVR向上の第一歩です。
ランディングページの導線とデザイン改善
次に、ランディングページ(LP)のデザインや構成を見直します。特に重要なのが、ページを開いて最初に目に入る「ファーストビュー」です。ここで「自分に関係がある」「メリットがある」と思ってもらえなければ、続きを読んでもらえません。
- キャッチコピー: ユーザーの悩みに寄り添っているか
- CTAボタン: 「申し込み」ボタンは目立つ色や場所にあるか
これらを改善するだけでも、反応が変わることがあります。ユーザーを迷わせない、スムーズな導線作りを心がけましょう。
入力フォームの最適化(EFO)
「入力フォームの最適化(EFO)」も非常に効果的です。せっかく「買いたい」と思ったのに、住所や名前の入力が面倒で諦めてしまった経験はありませんか?
- 入力項目を必要最小限に減らす
- 郵便番号から住所を自動入力できるようにする
- エラー表示をわかりやすくする
このように入力のストレスを減らすだけで、カゴ落ち(購入直前の離脱)を防ぎ、CVRを改善できます。今日からでもできる施策なので、ぜひ試してみてください。
ページの表示速度とモバイル対応の強化
最後に、ページの表示速度とモバイル対応です。Googleの調査によると、表示速度が1秒から3秒に落ちるだけで、離脱率は32%も上昇すると言われています。
サイトがサクサク動くことは、ユーザー体験の基本です。画像のサイズを圧縮したり、不要なプログラムを削除したりして、表示速度を改善しましょう。また、スマホで見やすいレイアウトになっているか(文字サイズやボタンの大きさなど)も、改めてチェックしてみてくださいね。
まとめ
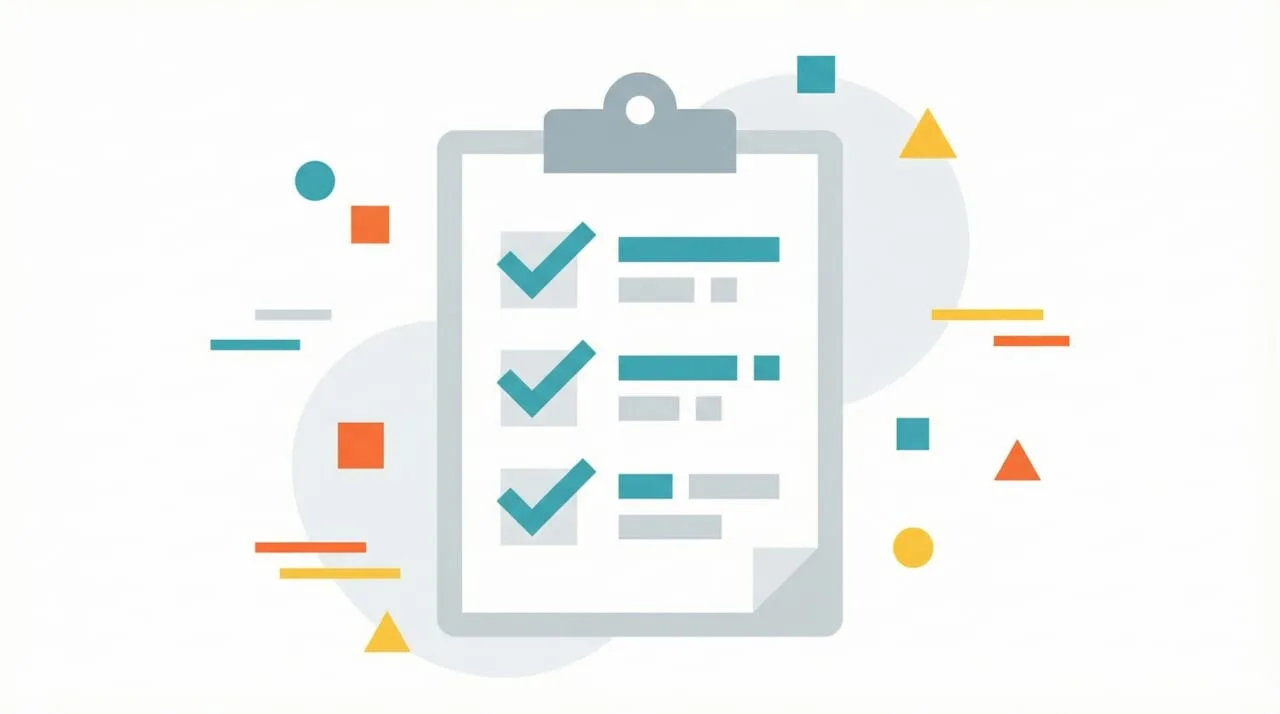
今回は、「cvr 平均」をテーマに、業界別や媒体別の目安、そして改善策について解説してきました。
記事のポイント:
- 全体の目安: 一般的なCVR平均は2〜3%程度だが、業界によって大きく異なる。
- 業界別の違い: ECは1〜3%、BtoBは2〜5%(資料請求等)、金融は高めの傾向。
- 媒体別の違い: リスティング広告やメルマガは高く、ディスプレイ広告は低め。
- 改善の鍵: 流入キーワードの見直し、LP改善、フォーム最適化、スマホ対応が有効。
平均値はあくまで「健康診断の基準値」のようなものです。大切なのは、平均と比較して一喜一憂することではなく、自社の過去のデータと比較して成長しているか、そしてボトルネックを見つけて改善し続けることです。
まずは自社の現状を把握し、できるところから一つずつ改善に取り組んでみてくださいね。地道な改善が、大きな成果につながるはずです。
cvr 平均についてよくある質問

最後に、CVRや平均値についてよく寄せられる質問をまとめました。疑問を解消して、スッキリした状態で施策に取り組みましょう。
- Q1. CVRの合格ラインはどれくらいですか?
- 業界や目的によりますが、一般的には1%〜2%あれば極端に悪い状態ではありません。まずは自社の業界平均を目指し、その後は過去の自社データを超え続けることを目標にしましょう。
- Q2. CVRが急に下がってしまいました。原因は何が考えられますか?
- 季節要因、広告のターゲット変更、サイトの不具合、競合他社のキャンペーンなどが考えられます。まずはアクセス解析で「どのページで」「どのデバイスで」下がったのかを特定しましょう。
- Q3. コンバージョン率を上げる一番手っ取り早い方法は?
- 入力フォームの改善(EFO)が即効性が高いです。入力項目を減らしたり、必須項目をわかりやすくしたりするだけで、その日から数値が改善することも珍しくありません。
- Q4. CVRが100%を超えることはありますか?
- 基本的にはありませんが、計算式上の定義によってはあり得ます(例:1回の訪問で複数回コンバージョンできる設定など)。しかし、通常は100%以下になります。
- Q5. セッション数とPV数、どちらで計算するのが正しいですか?
- 一般的にはセッション数(訪問数)を分母にします。1回の訪問で何ページ見ても、購入のチャンスは1回(1訪問)と考えるのが自然だからです。


