「突然、サイトのアクセス数がガクンと減ってしまった…」
「検索順位がいきなり圏外に飛んでしまったけれど、何が起きたの?」
一生懸命運営しているWebサイトやブログでこんなことが起きると、本当に焦ってしまいますよね。その原因、もしかすると「Googleアルゴリズムアップデート」かもしれません。
Googleは検索ユーザーにより良い情報を届けるため、定期的に検索結果の順位を決めるルール(アルゴリズム)を変更しています。これがアップデートです。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、Googleアルゴリズムアップデートの仕組みや歴史、そして万が一順位が下がってしまった時の具体的な対策について解説します。
正しい知識を持っていれば、必要以上に怖がることはありません。一緒に一つずつ確認していきましょう。
このページに書いてあること
Googleアルゴリズムアップデートとは?基礎知識を解説

まずは、Googleアルゴリズムアップデートの基本についてお話ししますね。
専門用語のように聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば「Googleの検索順位を決めるルール変更」のことです。なぜGoogleは頻繁にルールを変えるのか、その仕組みと理由を知ることで、対策の第一歩を踏み出せますよ。
検索順位が決まる仕組みとアルゴリズムの関係
Google検索でキーワードを入力したとき、どのサイトを1番目に表示するかを決めている計算式やルールのことを「アルゴリズム」と呼びます。
このアルゴリズムは、200以上の要素から成り立っていると言われています。まるで学校の成績表のように、「記事の質」「サイトの使いやすさ」「情報の正確さ」など、さまざまな項目で点数をつけて順位を決めているんです。
Googleアルゴリズムアップデートとは、この「採点基準」が見直されること。今まで評価されていたポイントが変わるため、順位に変動が起きるわけですね。
日々の更新と大規模な「コアアップデート」の違い
実は、Googleは毎日のように小さな調整(アップデート)を行っています。これらは微調整なので、順位に大きな影響を与えることはあまりありません。
一方で、年に数回行われる大規模な変更を「コアアップデート(Core Algorithm Update)」と呼びます。これは、検索結果の品質を大きく向上させるための全面的な見直しです。
例えるなら、日々の更新は「小テスト」、コアアップデートは「期末テスト」や「通知表の評価基準の変更」のようなもの。コアアップデートの時期には、多くのサイトで順位が大きく動く傾向があります。
Googleがアップデートを頻繁に行う目的とユーザーファースト
「せっかく順位が安定していたのに、なんで変えるの?」と思うかもしれませんね。でも、Googleがアップデートを行う目的は、決してサイト運営者を困らせることではありません。
最大の目的は「ユーザーファースト」。つまり、検索を使う人にとって、より便利で、正確で、役に立つ情報を届けるためです。
時代とともに情報の形やユーザーの悩みは変化します。古い情報のままではユーザーを満足させられませんよね。Googleは常に「検索する人にとって最良の結果」を目指して進化し続けているのです。
【年代別】過去の主要なGoogleアルゴリズムアップデートの歴史
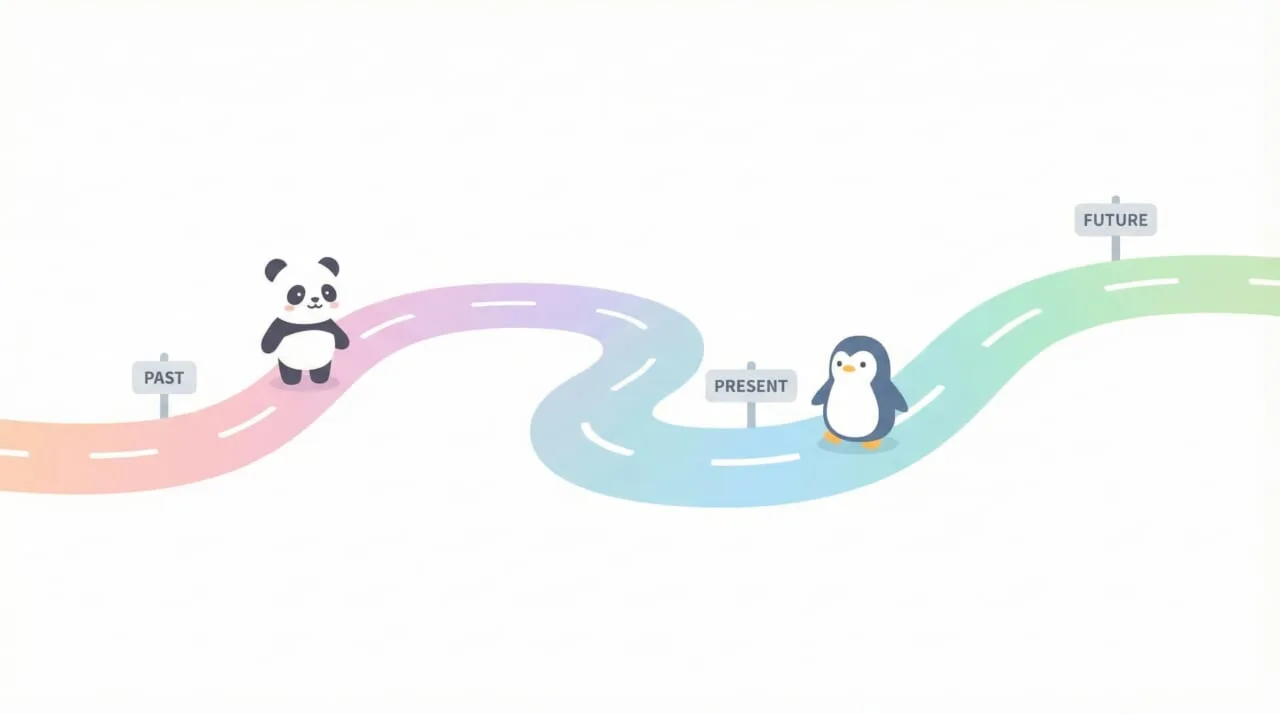
Googleはこれまでに何度も大きなアップデートを行ってきました。過去の歴史を振り返ることで、「Googleが何を嫌い、何を評価しようとしてきたか」という大きな流れが見えてきます。
ここでは、SEOの歴史を変えた主要なアップデートを年代順にご紹介しますね。動物の名前がついたものも多くて、少し面白いですよ。
パンダアップデート(品質の低いコンテンツへの対策)
2011年頃から導入された「パンダアップデート」は、中身の薄いコンテンツや、他のサイトをコピーしただけの質の低いサイトの順位を下げるための変更です。
それまでは、質が低くてもキーワードを詰め込めば上位表示できてしまうことがありました。しかし、このアップデートによって「ユーザーにとって価値のあるオリジナルコンテンツ」が正当に評価されるようになったのです。「白黒はっきりつける」という意味でパンダと覚えるといいかもしれませんね。
ペンギンアップデート(不自然なリンクへの対策)
2012年に導入された「ペンギンアップデート」は、検索順位を上げるためだけに作られた不自然なリンク(スパムリンク)を取り締まるためのものです。
かつては、自作自演で大量のリンクを貼る手法が流行していました。ペンギンアップデートはそうした不正を厳しく判定し、ズルをして順位を上げようとするサイトを排除しました。これにより、正当な努力をしているサイトが評価される環境が整ったのです。
ハミングバードアップデート(検索意図の理解向上)
2013年の「ハミングバードアップデート」は、検索キーワードの「意味」や「文脈」を理解する能力を向上させたものです。
単語そのものだけでなく、「会話のような複雑な質問」に対しても、ユーザーが本当に知りたい答えを推測して返せるようになりました。例えば「近くの美味しいカフェ」と検索した時に、単語の一致だけでなく、場所や評判などの意図を汲み取れるようになったのは、この進化のおかげです。
ベニスアップデート(位置情報と検索結果の連動)
「ベニスアップデート」によって、ユーザーがいる「位置情報」が検索結果に大きく反映されるようになりました。
例えば、東京で「ラーメン屋」と検索するのと、大阪で検索するのとでは、表示されるお店が違いますよね。これはベニスアップデートの影響です。地域に根ざしたビジネスをしている方にとっては、ローカルSEO(MEO)の重要性が高まったきっかけといえるでしょう。
モバイルフレンドリーアップデート(スマホ対応の重視)
スマートフォンの普及に伴い、2015年に実施されたのが「モバイルフレンドリーアップデート」です。スマホで見にくいサイトよりも、スマホ対応して見やすいサイトを優先的に評価するという変更でした。
文字が小さすぎたり、リンクが押しにくかったりするサイトは、スマホでの検索順位が下がってしまう要因になります。今ではスマホ対応は当たり前のことですが、当時は大きな転換点でした。
ランクブレイン(AIによる検索クエリの解釈)
2015年に導入された「ランクブレイン」は、AI(人工知能)技術を活用して、初めて見る検索クエリや曖昧な言葉の意味を解釈するシステムです。
これにより、Googleは過去に検索されたことのない言葉でも、類似のパターンから推測して、関連性の高い結果を表示できるようになりました。機械学習によって、検索エンジンがより賢くなった瞬間です。
モバイルファーストインデックス(MFI)(評価基準のスマホ移行)
「モバイルファーストインデックス(MFI)」は、評価の基準をパソコン版のサイトからスマホ版のサイトへ切り替えるという、非常に大きな変更でした。
以前はパソコン用のページを見て順位を決めていましたが、スマホユーザーが圧倒的に増えたため、Googleも「スマホ版の内容」を基準(主)にすることにしたのです。レスポンシブデザインなどで、スマホでもPCと同じ情報を提供することが必須となりました。
健康アップデート(医療・健康分野の信頼性重視)
2017年頃、日本で特に大きな影響があったのが通称「健康アップデート」です。医療や健康に関する情報(YMYL:Your Money or Your Life)において、情報の信頼性や専門性が厳格に求められるようになりました。
どこの誰が書いたかわからない医療記事よりも、医師や専門機関が発信する情報が優先されるようになったのです。命に関わる分野だからこそ、Googleも慎重に評価しています。
BERTアップデート(自然言語処理技術の進化)
2019年に導入された「BERT(バート)」は、自然言語処理技術の飛躍的な進化です。文章の文脈、特に「〜から」「〜へ」といった助詞のニュアンスまで理解できるようになりました。
これにより、より人間が話す言葉に近い感覚で検索意図を理解できるようになり、ロングテールキーワード(複数の単語を組み合わせた検索)の精度が向上しました。ユーザーの細かい悩みに寄り添えるようになったと言えます。
ページエクスペリエンスアップデート(使いやすさの指標化)
2021年の「ページエクスペリエンスアップデート」では、Webサイトの「使いやすさ(UX)」がランキング要因に組み込まれました。
具体的には、ページの読み込み速度、操作への反応速度、レイアウトの安定性(Core Web Vitals)などが評価対象です。コンテンツの内容が良いことは大前提として、「見ていてストレスがないか」「快適に閲覧できるか」も大切にされるようになったのです。
ヘルプフルコンテンツアップデート(ユーザーの役に立つ情報の評価)
2022年から始まった「ヘルプフルコンテンツアップデート」は、その名の通り「人の役に立つコンテンツ」を高く評価し、検索エンジン向けに作られただけのコンテンツの評価を下げるものです。
「とりあえず文字数を増やしただけ」「中身がないまとめ記事」などは評価されにくくなりました。書き手が誰かに向けて書いた、独自性のある有益な情報かどうかが厳しくチェックされています。
スパムアップデート(不正な手法に対する取り締まり強化)
Googleは常にスパム(不正行為)と戦っていますが、近年その対策はさらに強化されています。これが「スパムアップデート」です。
自動生成された無意味なテキスト、クローキング(検索エンジンとユーザーに違う内容を見せる行為)、ハッキングされたコンテンツなどを検知して排除します。真面目に運営しているサイトを守るための、警察のような役割を果たしているアップデートですね。
直近のGoogleアルゴリズムアップデートの傾向【2024年〜2025年版】

SEOの世界は日々変化しています。特に2024年から2025年にかけては、AIの台頭もあり、Googleの評価基準も新しいフェーズに入っています。
ここでは、今まさに注目されている最新の傾向について解説します。これを知っておくことで、これからのサイト運営の指針になりますよ。
検索結果におけるAI生成コンテンツへの対応方針
生成AIの普及により、AIで書かれた記事が急増しました。Googleは「AIだからダメ」とは言っていませんが、「AIで作っただけの質の低いコンテンツ」には厳しい対応をとっています。
重要なのは、誰が(何が)書いたかよりも「内容の質」です。AIを使っても良いですが、必ず人間が監修し、独自の視点や情報を加えることが求められます。単なるコピペのようなAI記事は、検索結果から除外されるリスクが高まっています。
ドメイン貸しや寄生サイトに対する評価の厳格化
最近の傾向として、評価の高い大手サイトのドメインの一部を借りて、全く関係のないアフィリエイトサイトなどを運営する「ドメイン貸し(寄生サイト)」への対策が強化されています。
「サイトの評判を悪用したスパム」とみなされ、評価が厳格化されました。これにより、本来のサイトテーマと無関係なコンテンツを大量に掲載しているサイトは、順位を大きく落とす事例が増えています。
大量生成された低品質コンテンツへのスパム対策
AIなどを悪用して、大量の低品質なページを短期間で生成し、検索結果を埋め尽くそうとする手法に対するスパム対策も強化されています。
「大量生成されたコンテンツ」は、ユーザーにとってノイズでしかありません。Googleはこうした行為を「スケールド・コンテンツ・アビューズ(規模を拡大したコンテンツの悪用)」と定義し、厳しく取り締まっています。量より質の時代が、より鮮明になっていますね。
独自性や実体験(Experience)を重視する流れの加速
今、最も重視されているのが「E-E-A-T」の中の「E(Experience:経験)」です。一般的な情報だけでなく、「実際にやってみた」「行ってみた」という一次情報がこれまで以上に高く評価されるようになりました。
どこかのサイトをまとめただけの記事よりも、あなた自身の体験談や独自写真、感想が含まれている記事が優遇されます。これはAIには真似できない、人間ならではの強みになります。
サイト全体のテーマ性と専門性の評価比重
サイト全体が「何の専門家なのか」というテーマ性も重要視されています。あれもこれもと手当たり次第にジャンルを広げるよりも、特定の分野に特化しているサイトの方が、専門性が高いと判断されやすくなっています。
「このサイトなら〇〇について詳しい」とGoogleにもユーザーにも認識されることが、安定した順位獲得への近道です。トピッククラスター(関連記事の集合体)を意識した構成が有効でしょう。
自分のサイトがアップデートの影響を受けたか確認する方法

「アクセスが減った気がするけど、本当にアップデートのせい?」と不安に思ったら、まずは事実確認から始めましょう。
感覚だけで判断せず、ツールを使ってデータを見ることで、冷静に対処できます。ここでは、初心者の方でも簡単にできる確認方法をご紹介します。
Googleサーチコンソールで検索順位と表示回数の推移を見る
まずは「Googleサーチコンソール」を確認しましょう。「検索パフォーマンス」のレポートで、アップデートが発表された日付前後の「平均掲載順位」と「表示回数」のグラフを見ます。
もし、特定の日を境にグラフがガクンと下がっているなら、アップデートの影響を受けた可能性が高いです。どのキーワードやページが下がったのかまで特定できるので、対策の手がかりになりますよ。
Googleアナリティクスでアクセス数の急減がないか調べる
次に「Googleアナリティクス」でサイト全体のアクセス数(ユーザー数やセッション数)を見てみましょう。
季節による変動(トレンド)などもありますが、アップデートの影響なら、ある日突然、崖から落ちるようにアクセスが減ることが多いです。検索エンジン(Organic Search)からの流入だけが急減していないかチェックしてみてください。他のSNSなどからの流入が変わらなければ、SEOの問題だと絞り込めます。
検索順位チェックツールで順位変動の幅を確認する
日頃から「GRC」や「Nobilista」などの検索順位チェックツールを使っている場合は、順位変動の幅を確認しましょう。
1位〜2位程度の変動なら誤差の範囲ですが、10位以上落ちたり、圏外に飛んだりしている場合は要注意です。自分のサイトだけでなく、競合サイトの順位も一緒に動いているかどうかも見ると、業界全体の変動なのか自社だけの問題なのかがわかります。
Google検索セントラルや公式X(旧Twitter)で最新情報を集める
Googleは、大きなアップデートがある場合に「Google検索セントラル」のブログや、公式X(旧Twitter)アカウント(@googlesearchcなど)で情報を発信します。
「今、アップデートを展開中です」といったアナウンスがないか確認しましょう。また、SEOの専門家たちがSNSで変動状況を実況していることも多いので、「#SEO」「#Googleアップデート」などのハッシュタグで検索してみるのも情報収集に役立ちます。
検索順位が急落した場合の具体的な対処法とSEO対策

もし確認した結果、アップデートの影響で順位が急落していたとしても、慌てないでください。焦って間違った修正をすると、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。
ここでは、順位が下がった時にとるべき正しい行動と、具体的な修正ポイントをステップ形式で解説します。
順位変動が落ち着くまで1〜2週間ほど様子を見る
アップデート直後は順位が乱高下することがよくあります。今日下がっても、明日には戻っていることもしばしば。Google側も調整を行っている最中なので、完全に展開が完了するまで(通常1〜2週間程度)は、静観するのが賢明です。
焦って記事を大幅に書き換えたり削除したりすると、何が原因で順位が変わったのか検証できなくなってしまいます。まずは深呼吸して、嵐が過ぎ去るのを待ちましょう。
Googleの「品質評価ガイドライン」を読み直す
Googleは「検索品質評価ガイドライン」という資料を公開しています。これには「Googleがどんなページを高く評価するか」の答えが書いてあります。
特に「品質の低いページ」の定義などを読み直してみてください。「自分のサイトはこれに当てはまっていないか?」と客観的に見つめ直す良い機会です。英語の資料ですが、日本語で解説しているSEOブログなどもたくさんあるので参考にしてみましょう。
競合サイトと比較してコンテンツの質や網羅性を見直す
順位が上がった競合サイト(上位サイト)を分析しましょう。自分のサイトと何が違うのでしょうか?
「情報の網羅性が高い」「独自の図解がある」「専門家の監修がついている」など、負けているポイントが見つかるはずです。ただし、丸パクリはNG。あくまで「不足している要素」を見つけ、自分なりの言葉と方法でコンテンツを強化するためのヒントにしてください。
専門性・権威性・信頼性・経験(E-E-A-T)を強化する
今のSEOで最も重要なのが「E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・経験)」です。
プロフィールページを充実させる、運営者情報を詳しく書く、記事に監修者をつける、引用元を明記するなど、サイトの信頼度を高める施策を行いましょう。特に「経験(Experience)」として、自分だけの体験談や事例を記事に追加するのは非常に効果的です。
読者の検索意図(知りたいこと)に正しく回答できているか確認する
ユーザーがそのキーワードで検索したとき、本当に知りたいことは何でしょうか?検索意図(インサイト)と記事の内容がズレていると、順位は戻りません。
例えば「〇〇 使い方」で検索しているのに、商品の売り込みばかりしていませんか?ユーザーの悩みに対して、結論からわかりやすく、過不足なく回答できているか、記事の構成を根本から見直してみましょう。
ページの表示速度改善やモバイル対応など使いやすさを向上させる
コンテンツの中身だけでなく、サイトの「使い勝手」も改善しましょう。ページの表示速度が遅いと、ユーザーはすぐに帰ってしまいます。
画像のサイズを圧縮する、不要なプラグインを削除するなどして軽量化を図りましょう。また、スマホで見た時に文字が小さすぎないか、ボタンが押しやすいかなど、モバイルフレンドリーな設計になっているかも再確認してください。
質の低い記事をリライト(修正)または削除・統合する
サイト内に「質の低い記事」が大量にあると、サイト全体の評価足を引っ張ることがあります。
アクセスがほとんどなく、内容も薄い記事は、思い切って「リライト(加筆修正)」して質を高めるか、似たテーマの記事に「統合」しましょう。それでも改善が見込めない場合は、勇気を持って「削除(noindex)」することも、サイト全体の健康を守るための立派な戦略です。
過去に行った過剰なSEO対策や不自然なリンクを修正する
過去に「キーワードを不自然に詰め込む」「隠しテキストを入れる」「質の低いサイトから大量にリンクを貼る」などのSEO対策をしていませんか?
これらは現在ではスパムとみなされます。もし心当たりがあるなら、すぐに修正しましょう。不自然なリンクは否認ツールを使って無効化するなど、過去の「負の遺産」を清算することで、評価が回復することがあります。
今後のアルゴリズムアップデートに備えるための心構え
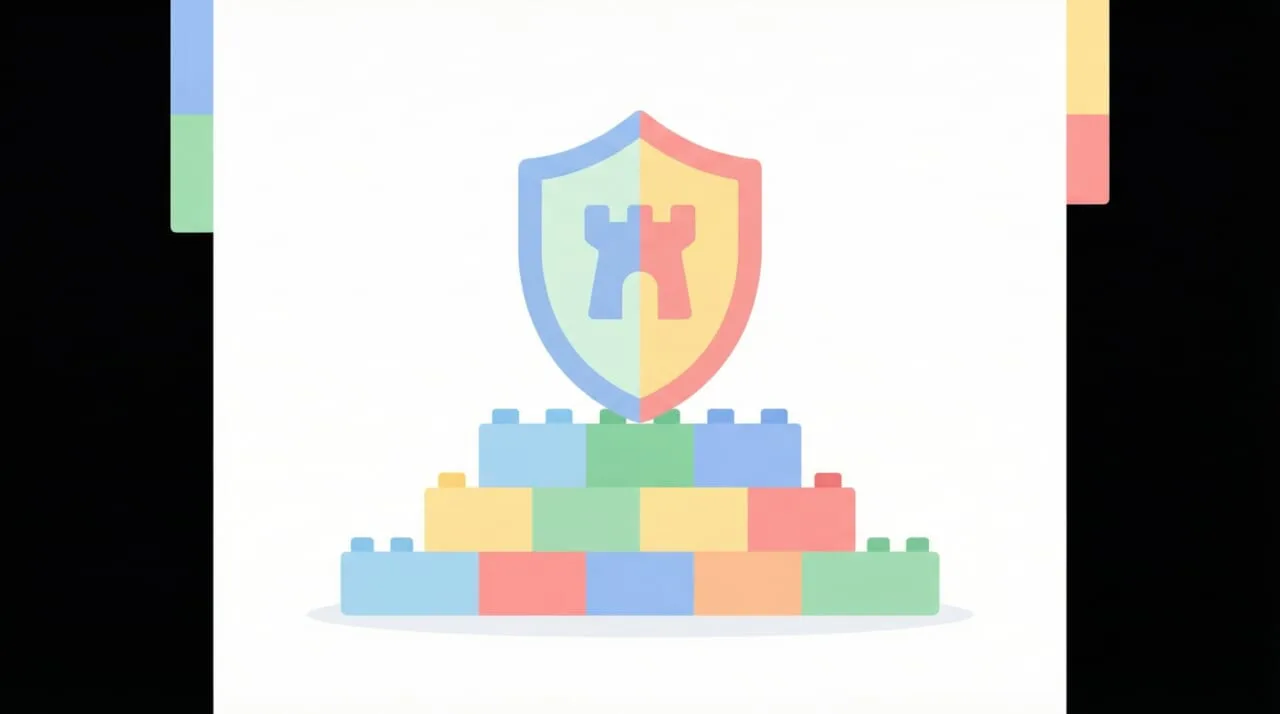
Googleアルゴリズムアップデートは今後も続きます。そのたびに一喜一憂するのは疲れてしまいますよね。
アップデートに振り回されない強いサイトを作るためには、小手先のテクニックではなく、本質的な心構えが大切です。最後に、これからの運営で意識すべきポイントをお伝えします。
テクニックよりも「ユーザーの役に立つか」を最優先する
アルゴリズムの裏をかこうとするテクニックは、いつか通用しなくなります。しかし、「ユーザーの役に立つこと」を目指していれば、Googleの方向性と一致するため、アップデートで評価が下がるリスクは低くなります。
「この記事を読んだ人は、悩みを解決して笑顔になれるか?」を常に自分に問いかけてみてください。Googleを見て記事を書くのではなく、画面の向こうにいる人間を見て書くことが、最強のSEO対策です。
一次情報(体験談や独自データ)を積極的に発信する
ネット上の情報をまとめただけの「コタツ記事」は、AIでも簡単に作れる時代になりました。だからこそ、あなたしか持っていない「一次情報」が輝きます。
実際に体験したこと、取材して得た話、独自の調査データなど、オリジナルな情報を積極的に発信しましょう。それは誰にもコピーできない強力な武器となり、Googleからもユーザーからも信頼される要因になります。
特定のキーワードだけでなくサイト全体の信頼性を高める
特定のキーワードで上位表示することだけに固執せず、サイト全体、あるいは運営者自身のブランド力を高めることも意識しましょう。
「この人の言うことなら間違いない」「このサイトはいつも参考になる」と指名検索されるようになれば、アルゴリズムの変動にも左右されにくい、盤石な基盤ができます。SNSなども活用して、ファンを増やしていくことが、長期的な安定につながります。
まとめ

Googleアルゴリズムアップデートは、検索ユーザーにより良い検索体験を届けるための改善プロセスです。順位が下がると焦ってしまいますが、それは「もっとユーザーの役に立つサイトになれるチャンス」でもあります。
- まずは冷静に状況を確認する
- 小手先の対策ではなく、コンテンツの質(E-E-A-T)を見直す
- ユーザーファーストを徹底する
これらを意識して運営を続ければ、アップデートは決して怖いものではありません。一時的な変動に惑わされず、読者にとって本当に価値のある情報を積み重ねていきましょう。そうすれば、結果は自然とついてきますよ。
googleアルゴリズムアップデートについてよくある質問

Q1. アルゴリズムアップデートはいつ行われますか?
コアアップデートのような大規模なものは年に数回(2〜4回程度)行われます。具体的な日時はGoogleから直前に発表されることが多いですが、日々の小さな更新は予告なく常に行われています。
Q2. 順位が下がったらすぐに記事を修正すべきですか?
いいえ、すぐには修正せず、1〜2週間ほど様子を見ましょう。アップデート展開中は順位が不安定になるため、変動が落ち着いてから原因を分析し、対策を行うのが確実です。
Q3. 一度下がった順位は元に戻りますか?
適切な改善を行えば、戻る可能性は十分にあります。ただし、以前と全く同じ順位に戻るとは限りません。場合によっては数ヶ月かかることもありますが、諦めずにコンテンツの質を高めることが大切です。
Q4. どんなサイトがアップデートの影響を受けやすいですか?
医療・健康・金融などのYMYL分野のサイトや、低品質なコンテンツが多いサイト、他サイトのコピーコンテンツが多いサイトなどが影響を受けやすい傾向にあります。
Q5. アップデート情報はどこで確認できますか?
Google検索セントラルのブログや、Google公式のX(旧Twitter)アカウント「Google Search Central」で最新の発表を確認できます。


